すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
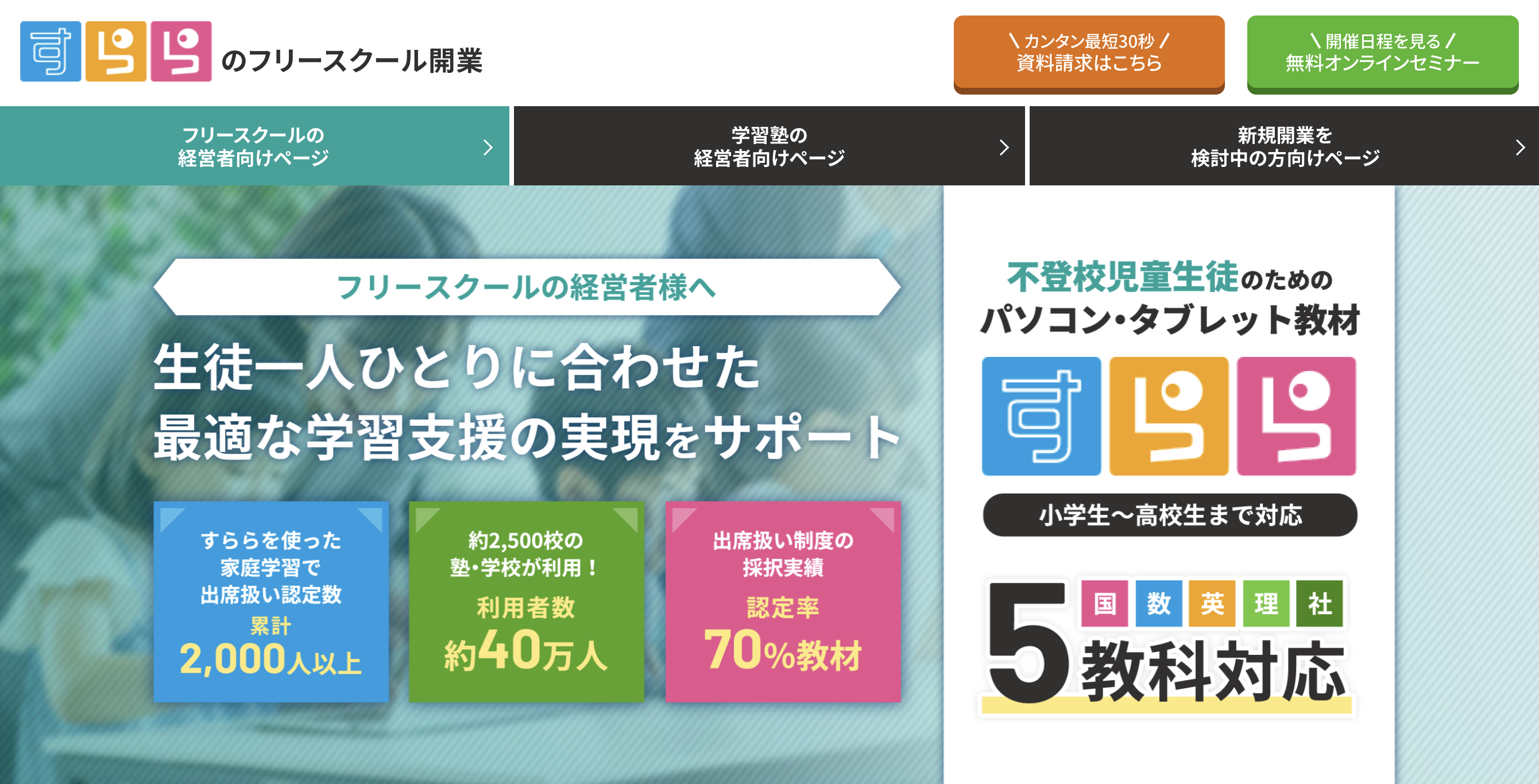
不登校が続いてしまうと、「このまま学校に行けなかったらどうなるの?」「出席日数が足りなくて進級に影響が出るのでは?」と不安に感じる保護者の方も多いと思います。
そんな中、注目されているのが、家庭での学習を学校の「出席扱い」として認めてもらう制度です。
文部科学省のガイドラインでは、一定の条件を満たせば、在宅でのICT教材などによる学習活動を出席扱いとして認めることができるとされています。
すららはその条件をしっかり満たす構造を持っており、実際に多くの学校で出席扱いが認定された実績があります。
ここでは、なぜすららが不登校でも出席扱いになりやすいのか、その理由や仕組みについて具体的に解説していきますね。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは単なる自宅学習ツールではなく、学習の「質」と「記録性」が明確な教材です。
そのため、学校に対して「この子はきちんと学習している」という証拠をしっかり提出できるのが強みです。
特に不登校のケースでは、家庭で何をどれだけ学習しているかを学校側が把握するのが難しいため、この記録性の高さは大きな安心材料になります。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習時間や正答率、進捗状況などが自動で記録され、レポートとして出力できます。
このレポートを担任や教育委員会に提出することで、「どの教科をどのくらいやっているか」が明確に伝わります。
紙のドリルや口頭での説明よりも、客観的な証拠として評価されやすいのが特徴です。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
保護者がわざわざ記録をつけなくても、すらら側で学習履歴がすべて可視化される仕組みになっています。
学校の先生は、学習状況がリアルタイムで見えることに安心感を持ちやすく、「家庭での学習が継続されている」と判断されやすくなります。
親子ともに無理なく提出できる点も、続けやすさにつながっています。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子どもにとって、いちばん大切なのは「自分に合ったペースで学べること」と「継続できる環境があること」です。
すららはその両方を満たせるように、AIによる分析+コーチによる伴走サポートを組み合わせて、学習計画を柔軟に調整してくれます。
そのため、学校側にも「無理のない計画で継続できている」という点がしっかり伝わりやすくなるのです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららコーチは、学習の進め方やスケジュールの管理をサポートしてくれる存在です。
計画的に進められる仕組みと、必要に応じて見直しができる柔軟さがあることで、「続けられる学習」として学校側にも好印象を与えることができます。
単なる“自習”ではなく、伴走支援があることが、出席扱いとして認められやすい理由のひとつです。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
学習が続かない最大の原因のひとつは「計画が立てられない」ことですが、すららは専任のコーチが子どもの状態に合わせて計画を立ててくれます。
不登校で学習のリズムが崩れていても、「今日は何をすればいいか」が明確になり、継続しやすい環境がつくれます。
保護者がすべて管理しなくてもよくなるのも、大きな安心ポイントです。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは「学年」にとらわれず、今の理解度に合わせて自由にさかのぼり・先取りができる無学年式の教材です。
不登校で空白期間があっても、焦らず戻って学べるので、「わからないまま進む」ことがありません。
逆に得意な科目はどんどん先に進められるので、子ども自身のペースで進められる柔軟さが出席認定の信頼にもつながっています。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららは「家庭」「学校」「教材提供側」が連携しやすい体制を整えているのが特長です。
出席扱いを認定してもらうためには、学習の記録だけでなく、学校側とのやりとりが円滑であることも重要になります。
すららでは、その橋渡しを専任コーチが丁寧にフォローしてくれるので、保護者が孤立しない点も安心材料のひとつです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いにしてもらうには、「学習状況報告書」などの提出が必要になるケースもありますが、すららでは必要な書類の書き方や流れも丁寧に案内してくれます。
「どこに何を提出すればいいの?」という保護者の不安を減らしてくれるサポートです。
初めての手続きでも、迷わずに進められるよう工夫されています。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
学校への提出用に、すららでは専用の学習レポートフォーマットが用意されています。
コーチがその作成や提出のタイミングについてもフォローしてくれるため、家庭側の負担は大きくありません。
「これで大丈夫かな」と不安にならずに済むサポート体制が整っています。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
すららでは、学校側と連携をとるための資料提供や説明資料も整備されており、保護者が担任や校長先生に説明しやすいよう配慮されています。
「この教材でこう学んでいます」と自信を持って伝えられることで、学校との信頼関係を築くことにもつながります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省から「教育利用にふさわしい教材」として認定を受けた実績を持ち、全国の自治体や学校で導入されています。
そのため、学校側も安心して「学習ツールとしての有効性」を評価しやすく、出席扱いの判断材料としても信頼されやすいのです。
この公式な立場が、家庭学習を出席にカウントする後押しになっています。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは多くの自治体や学校と連携しており、不登校の子どもに向けた支援実績も豊富です。
この実績があることで、学校側も「前例がある教材」として安心感を持ちやすく、柔軟に出席扱いを検討してもらえるケースが増えています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、公式に「不登校支援に適した教材」として紹介されており、自治体の資料などにも掲載されることがあります。
個人の自宅学習としてだけでなく、教育現場の中でも有効と認められている点が、出席扱いに結びつきやすい理由のひとつです。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとして認められるには、「家庭学習が学校に準ずる内容・質であること」が求められます。
すららはその条件を満たす構造を備えており、ただの“自習”ではなく、評価・指導・復習が組み合わさった学習システムとして設計されています。
これが学校側の「出席認定」の後押しになるポイントでもあります。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららで提供されている内容は、国語・算数・理科・社会・英語といった主要科目すべてが、文部科学省の学習指導要領に準拠して作られています。
つまり、学校の授業と同じ範囲・同じ水準で学べる内容になっているので、「学校に準ずる教材」として評価されやすいのです。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
単なる映像授業ではなく、すららでは学習した内容に対して即時フィードバックがあり、AIやコーチによる弱点補強も行われます。
「一方通行の学習」ではなく、きちんと評価と補強がセットになった学習環境であることが、学校からも認められる理由のひとつです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららを使った家庭学習は、不登校のお子さんにとって大きな支えになります。
ただ、「本当に出席扱いにできるの?」「どうやって申請すればいいの?」という声もよく聞かれます。
文部科学省の通知では、家庭でのICT教材による学習活動も、一定の条件を満たせば「出席扱い」として認められる制度があります。
すららはその条件をクリアしており、学習記録の証明や支援体制の整備があることで、実際に多くの子どもたちが出席扱いになっています。
このページでは、「すららを利用した出席扱いの申請方法」について、家庭側で準備すべき流れをわかりやすく紹介していきますね。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初にやるべきことは、学校に相談することです。
担任の先生や学年主任、場合によっては校長先生に直接、家庭で学習を続けていることを伝え、出席扱いの申請をしたい旨を相談してみましょう。
学校側がこの制度を知らない場合もあるため、すららの資料やガイドラインを一緒に渡すとスムーズに話が進みやすくなります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校によって必要な書類や対応が少し異なることがあります。
そのため、最初に学校へ相談した際に「どういった書類が必要か」「誰に何を提出するか」など、具体的な流れを確認しておくと安心です。
すらら側でも、提出に使える学習記録レポートなどの資料が用意されているので、活用しながら準備を進めましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由によっては、医師の診断書が必要になるケースもあります。
たとえば、適応障害や発達障害、起立性調節障害など、医学的な理由での不登校の場合、学校側から意見書の提出を求められることがあります。
すべてのケースで必要とは限りませんが、早めに準備しておくと安心です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
診断書の必要性は、学校の方針や教育委員会のルールによって異なります。
精神的な不調や発達特性による不登校の場合、「医師の見解」があることで、学校側も制度に則って対応しやすくなります。
通っている病院に相談すれば、学校提出用に書いてもらえることが多いです。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書を依頼する際には、「学校の出席扱い制度に使用したい」と伝えるとスムーズです。
内容としては、「不登校の状態にあること」「学習活動を家庭で継続することが望ましい」旨が書かれていればOKです。
通院先によっては即日発行できないこともあるので、早めに動くのが安心です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでは、学習時間・内容・進捗などがデータで記録され、出席扱い申請に使える「学習記録レポート」を作成できます。
このレポートはPDFなどで出力可能で、担任の先生や学校側に提出することで、学習の証明として活用されます。
「どれくらい学んでいるのか」が明確になるので、学校側の安心材料にもなります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから、学習の進捗レポートを簡単にダウンロードできます。
このレポートには、学んだ教科・単元・正答率・所要時間などが自動で記載されており、第三者が見ても学習の継続性が明確に伝わります。
担任や校長先生に提出する際の説明資料としても非常に役立ちます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いにするための正式な申請書は、学校側が作成しますが、その際に保護者が補足説明をしたり、必要書類を添付するサポートが求められます。
すららのレポートや医師の意見書とあわせて、「自宅でどのように学んでいるか」を丁寧に共有することが大切です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いになるかどうかの最終判断は、学校長や教育委員会の承認によって決まります。
すららのようなICT教材は、文部科学省の通知に基づいて出席扱いの対象として認められる条件を満たしているため、申請の土台としてはとても有利です。
その上で、学校との信頼関係や連携がスムーズにいくかどうかも大切なポイントです。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的に出席扱いとして認めるかどうかは、学校長の判断に委ねられます。
そのため、担任や学年主任と連携をとりながら、家庭での学習状況がきちんと伝わるようサポートしていくことが大切です。
コツコツ学習を続けた証拠があれば、前向きに検討してもらえるケースも多いです。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、学校だけでなく教育委員会への申請が必要な場合もあります。
その際は、学校側が窓口となって進めてくれることが多いので、保護者は必要な書類を学校に預けたり、確認をとる形で連携していきましょう。
すらら側でもフォーマットや説明資料が用意されているので安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の状態でも、すららなどのICT教材を活用して自宅学習を継続していると、一定の条件を満たすことで学校から「出席扱い」として認められることがあります。
この制度は、単に出席日数を補うだけでなく、子どもにとっても保護者にとっても、さまざまな面で大きなメリットがあります。
たとえば、進学時の内申点や評価に関係する可能性もあり、「勉強していても評価されない」という不安を減らすきっかけにもなります。
また、学習が続けられているという事実が子どもの自己肯定感にもつながり、家庭での安心感や心の安定にもつながります。
ここでは、すららを通じて出席扱いを認めてもらうことで得られるメリットについて、わかりやすくご紹介していきますね。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席扱いにしてもらえることで、単純に「欠席日数が多い=評価が下がる」という状態を防ぐことができます。
内申点は、出席状況や学習態度、提出物なども含めて総合的に判断されるため、家庭での学習がきちんと認められることは非常に大きな意味があります。
将来の高校受験や進学にもつながる評価なので、安心して進路を考えることができるようになります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
すららでの学習が「出席扱い」としてカウントされれば、出席日数の不足によって内申点が極端に下がるのを防ぐことができます。
これは、中学や高校での内申点が重視される場合において、将来的な進学の選択肢を狭めないという意味でも重要です。
頑張っている努力が正当に評価されることは、子どもにとっても自信につながります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数が記録されていることで、内申点をベースにした進学選択でも有利に働く場合があります。
また「ちゃんと勉強していた」という事実がレポートや資料で示せることで、面接や個別相談の場でも好印象につながることがあります。
進路の幅を広げる意味でも、出席扱いはとても価値のある制度です。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が続くと、「授業に追いつけない」「もう勉強は遅れすぎている」という焦りや不安を子ども自身が感じてしまうことがあります。
でも、すららの無学年式学習で自分のペースで学べば、「今の自分から始められる」という安心感が生まれ、過度なプレッシャーを感じずに済みます。
このことは心の安定にもつながり、学びを続ける土台になります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは教科書に準拠した教材で、小学校から中学校まで幅広い範囲をカバーしています。
そのため、途中から学び直してもOKですし、得意な教科は先取りすることもできます。
「やっていない単元がある」という気持ちを抱えず、自分なりのスピードで進められるのが大きな安心材料になります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「学校に行けない自分はダメなんじゃないか」と思ってしまう子どもも少なくありません。
でも、すららのように褒めてくれるキャラクターや、コーチからのフィードバックがあると、「ちゃんとやれている」と実感しやすくなります。
毎日続けることがそのまま自信になり、自己肯定感を守る大きな支えになります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを支える保護者にとって、「勉強はどうするのか」「このままで大丈夫なのか」という不安は尽きません。
でも、すららで出席扱いが認められれば、最低限の学習面の安心が得られ、精神的な負担もグッと軽くなります。
すららコーチとの連携があることで、親だけで全てを抱え込まなくてもよくなります。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららは、コーチが学習面をサポートし、学校との連携に必要なレポートなども整えてくれます。
保護者は「勉強させなきゃ」と頑張るよりも、「一緒に見守る」という形で関わることができ、負担が軽減されます。
周囲と協力して子どもを支える体制が整うことで、親も心のゆとりを持つことができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを使った家庭学習が出席扱いとして認められる制度は、不登校の子どもとその家族にとって大きな支えになります。
ただし、この制度は誰でも自動的に適用されるわけではなく、いくつかの条件や手続き、そして学校側との連携が必要になります。
「すららなら大丈夫」と思っていても、申請の進め方や説明の仕方次第では、スムーズに承認が得られないケースもあるため、注意が必要です。
ここでは、すららを利用して出席扱いを目指すうえで、特に気をつけたいポイントをまとめました。
学校への説明のコツや医師への相談時の工夫など、現場でつまづきやすい点も含めてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを使って家庭で学習をしていても、最終的に出席扱いになるかどうかは学校長の判断によるため、まずは学校側にしっかりと説明することが大切です。
特に「ICT教材を使った学習が制度的に認められている」という前提を理解してもらうことが、出席扱いの第一歩となります。
担任だけでなく、教頭先生や校長先生にも早めに相談しておくと安心です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省が出している出席扱いの条件を満たす教材として設計されています。
その点を学校側にしっかり伝えることで、家庭学習が評価される根拠になります。
資料を見せながら説明することで、先生たちも納得しやすくなりますし、誤解を避ける助けにもなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
出席扱いに関しては、担任の先生だけで判断できないケースがほとんどです。
そのため、最初から教頭先生や校長先生に直接説明をするのがスムーズです。
その際、すららの学習記録やパンフレットなどを一緒に持参すると、具体的なイメージが伝わりやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、医療機関の診断書や意見書の提出を求められることがあります。
たとえば、起立性調節障害・適応障害・うつ症状などの体調や精神的な理由が背景にある場合、医師の見解が学校側の判断材料になることも多いです。
必要に応じて、あらかじめ診断書を準備しておくと安心です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
教育委員会や学校によっては、「不登校の理由が医学的なものである」ことを明確にするために、医師の書類を必須としているところもあります。
診断書があることで、制度的な根拠が強まり、出席扱いの申請が通りやすくなるケースもあります。
判断に迷った場合は、まず学校に確認してみましょう。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
普段通院している病院で、「学校に出席扱いとして認めてもらうための診断書が必要です」と具体的に伝えると、スムーズに対応してもらえることが多いです。
医師側も教育現場との連携に慣れている場合があり、適切な書き方で対応してくれることがほとんどです。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
ただ「不登校です」と書いてもらうだけでなく、「本人は家庭で学習意欲があり、継続して取り組んでいる」ことも伝えるのがポイントです。
そうした情報をもとに、医師が前向きな内容を診断書に記載してくれることで、学校側も安心して出席扱いを検討しやすくなります。
保護者として、状況を丁寧に伝えることが重要です。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いの制度は、家庭での学習が「学校に準じた教育内容」として認められることが前提になります。
つまり、ただの自習や好きな科目だけをやる学習スタイルでは不十分で、「学校での授業と同等の質・量の学び」が求められるのです。
すららのような教材を使って、主要教科をバランスよく学び、一定時間の学習を継続していることが重要になります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
出席扱いに認定されるためには、保護者の手作りプリントやYouTube学習などの「自由学習」ではなく、学校の教科書や指導要領に準拠した教材を使っていることが大切です。
すららは、文科省の学習指導要領に沿った内容が体系的に構成されているので、その点で信頼性があります。
学校側にも、「単なる自習ではない」という点を明確に伝えておきましょう。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いには「継続した学習」が必要です。
明確な基準はありませんが、1日あたり2〜3時間程度を目安に学習することで、学校の授業時間に近い学習量が確保できます。
無理をせず、お子さんの体調や集中力に合わせて時間を調整しながら、トータルで見て「しっかり学んでいる」実績を残せるように意識すると良いです。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
「国語・数学(算数)・英語・理科・社会」といった主要5教科をバランスよく学ぶことが出席扱いの条件になるケースもあります。
特定の教科ばかりに偏ってしまうと、「学校に準じた教育活動」として認められにくくなることがあります。
すららなら、必要に応じて教科追加ができるので、お子さんの状況に応じて調整していくと安心です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いの申請や継続には、「家庭でどのように学んでいるか」を学校側にきちんと共有していくことが不可欠です。
担任の先生との連絡が途絶えてしまうと、制度の継続も難しくなる可能性があります。
学習レポートの提出や電話・面談を通じて、学校と家庭が連携しているという姿勢を示すことが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校側にとっては、「家庭での学習が続いているか」を定期的に把握することが求められます。
このため、保護者は学習記録や進捗状況をこまめに学校に伝える必要があります。
すららのレポートを活用すれば、負担をかけずに客観的なデータを共有できるのでおすすめです。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、月ごとの学習レポートを簡単にPDF形式で出力することができます。
月に1回程度、学校へこのレポートを提出することで、「学習が継続している」という証明になります。
学校側も安心できる材料になるので、習慣化しておくとスムーズです。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校側から家庭訪問や面談の提案があった場合は、できる限り前向きに対応しましょう。
家庭での学習環境やお子さんの様子を直接見てもらうことで、学校側が納得しやすくなります。
実際に顔を合わせて話をすることで、信頼関係が深まり、より柔軟な対応をしてもらえることもあります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
「まだ学校に行けないけれど、家庭で学習は頑張っています」という状況を、担任の先生と定期的に共有することが大切です。
メールや電話を通じて進捗を伝えるだけでも、学校とのつながりを感じられますし、出席扱いの判断材料としても有効です。
一方的な報告ではなく、相談として伝えるとよりスムーズです。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
自治体によっては、出席扱いを学校だけで判断するのではなく、教育委員会に正式な申請を行う必要がある場合もあります。
この場合、学校側と連携しながら、必要な書類の準備や手続きを進めていく形になります。
あらかじめその可能性を把握しておくことで、慌てずに対応できます。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に提出する資料には、医師の診断書や学習記録のほか、学校長の推薦状や学習支援計画が必要になることもあります。
これらは学校と保護者が協力して整えることが基本です。
すららのサポートやコーチからのアドバイスを活用しながら、書類をスムーズにそろえていくと安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを使った家庭学習で出席扱いを認めてもらうには、教材の質だけでなく、「どのように学校に伝えるか」「どんな姿勢で取り組んでいるか」も大切なポイントになります。
制度としては認められているものの、学校側が納得できる形で準備や説明を行わないと、スムーズに承認されないケースもあるのが現実です。
とはいえ、ちょっとした工夫や伝え方次第で、出席扱いのハードルはぐっと下がります。
すでに全国の多くの学校で「すららを使って出席扱いが認められた事例」もあり、しっかり準備すれば前向きな結果につながりやすいです。
この章では、学校側からの理解を得やすくなる「成功のコツ」や、「これをやってよかった」というポイントをわかりやすくご紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校によっては「ICT教材での出席扱い」という制度自体に馴染みがない場合もあります。
そのため、すららを使って出席扱いになった他の学校の事例を紹介することで、「うちでも導入できるかもしれない」と前向きに検討してもらえる可能性が高まります。
すららの導入実績は公式サイトにも掲載されているので、資料として活用すると効果的です。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
実際の学校名や地域が書かれた事例は、学校側にとって説得力のある材料になります。
「前例があるならうちでもできるかも」と思ってもらえることで、話が進みやすくなるからです。
保護者が丁寧に紹介する姿勢を見せることで、信頼感も生まれやすくなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すらら公式サイトには、不登校支援や出席扱い事例が掲載された実績ページがあります。
その中には教育委員会や学校と連携して取り組んでいる例もあるので、スクリーンショットやPDFでプリントして学校に持参するととても有効です。
説明の際に一緒に見せることで、学校側も納得しやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
制度や教材の説明だけではなく、「本人が前向きに取り組んでいる姿勢」も非常に大切な判断材料になります。
たとえ不登校であっても、家庭学習に意欲的に取り組んでいることが伝われば、出席扱いとして認められやすくなります。
学校との面談や提出資料の中で、本人の声を届ける工夫をしてみましょう。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
自分で書いた短い感想文や学習の目標などを提出すると、先生に「ちゃんと取り組んでいるんだな」と伝わりやすくなります。
書くことが難しい場合は、親が聞き取って代筆しても問題ありません。
小さな努力を形にすることが、出席扱いへの大きな一歩になります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
可能であれば、面談の場に本人も少しだけ同席して、「すららで勉強を頑張っています」と一言でも伝えると、とても効果的です。
直接話すことで、先生側の印象も大きく変わり、家庭と学校が協力しやすい雰囲気が生まれます。
無理のない範囲で、できるところから取り組んでみましょう。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いで最も重視されるのは、「継続性」です。
無理をしてたくさん勉強するよりも、本人が続けられる範囲で日々取り組めることの方が重要です。
継続できる計画を立てて、それを学校に提示することで、制度として認められやすくなります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
出席扱いは一時的な努力ではなく、継続的な学習姿勢が求められます。
そのためには、子どもの生活リズムや集中力に合わせて「無理のない計画」を立てることがとても大切です。
1日30分からでも、「続けられること」が最大のポイントです。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららのコーチは、学習の進め方やペース配分の相談にも丁寧に応じてくれます。
「毎日どれくらい進めればいいか」「どこから始めたらいいか」が不安なときは、コーチに相談して現実的な計画を一緒に立てるのがおすすめです。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららの最大の強みの一つが、学習コーチの存在です。
出席扱いの申請に必要な学習レポートや、学校への説明資料についても、コーチがサポートしてくれるため、保護者だけで抱え込まなくて大丈夫です。
制度の手続きに不安があるときは、遠慮せず頼ってみましょう。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチは、学習記録の出力方法や、学校に提出するレポートのまとめ方なども丁寧に教えてくれます。
必要に応じて、どのタイミングで何を提出すればいいかもアドバイスしてくれるので、制度への理解が浅くても安心です。
困ったときこそ、コーチのサポートを最大限活用しましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
すららは不登校の子どもたちにとって、学びの場を自宅に作ってくれる心強い味方です。
出席扱いを目指して導入する家庭も多く、実際に「学校から出席として認められた」「学習の継続で自己肯定感が回復した」といった前向きな声も数多く寄せられています。
今回は、すららを実際に利用した不登校の子どもや保護者の口コミをご紹介します。
最初は勉強に対して強い拒否反応があった子でも、「アニメでわかりやすかった」「ちょっとずつ進めるのが気楽だった」といったきっかけから、少しずつ学び直しが始まっています。
また、家庭の雰囲気が変わった、親子関係が改善されたという声も。
リアルな体験談から、「すららで出席扱いを目指すこと」にどれだけ希望があるのかを感じてもらえると嬉しいです。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
最初は毎日何をすればいいのかもわからず不安でいっぱいでしたが、すららを始めたことで学習の記録が自動で残り、それを学校に提出することで出席日数に加えてもらえました。
本人も「内申点がゼロになるかも」という不安が和らいで、自分のペースで頑張れるようになったのが大きかったです。
良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
すららは時間割を自分で決められるのがうちの子にはすごく合っていました。
学校だと決まった時間に合わせるのがつらかったけど、「今日は30分だけ」「明日はちょっと多めに」など、自由にできることでプレッシャーがなくなったようです。
良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
親としては「何もしない子ども」を見ているのがつらくて、毎日のように注意してしまっていました。
でも、すららを取り入れてからは、短時間でも「やった感」があるようで、本人の表情も明るくなり、私も落ち着いて見守れるようになりました。
良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
算数の授業が苦手で、「どうせ分からない」と諦めていたのですが、すららのアニメーション授業で少しずつ理解できるようになりました。
何度も繰り返せるし、自分のタイミングで進められるのがよかったみたいです。
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
「もう学校は行けないかも」と思っていましたが、家庭で学習を続けていたことで、子ども自身に少しずつ自信がついていったようです。
「今なら授業についていけるかも」と言ってくれて、最初は週1回だけの登校から、少しずつ教室に戻れるようになりました。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
不登校のお子さんがいると、「勉強はどうすればいい?」「内申点や出席日数は大丈夫?」と、親としては心配が尽きませんよね。
すららは、そんなご家庭に向けて開発されたタブレット学習教材で、出席扱い制度にも対応していることから注目されています。
でも、「制度って難しそう」「うちの子に合うのかな?」と、いざ始める前に気になる点があるのも当然のこと。
このページでは、すららに関してよく寄せられる質問に対して、ひとつひとつ丁寧にお答えしていきます。
口コミの真相、料金プラン、出席扱いの条件など、不安を解消するためのヒントが詰まっていますので、すららを検討中の方はぜひ参考にしてみてくださいね。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららの口コミの中には「キャラクターがうざい」「連絡がしつこい」と感じる声も一部あります。
これは、子どもの性格や年齢によって、アニメ調の授業やコーチからのサポートが「過干渉」と受け取られることがあるためです。
特に思春期の子や、自主性を重んじるタイプの子には向き不向きがあるかもしれません。
ただし、逆に「やる気が出た」「褒められて嬉しい」というポジティブな声も多く、好みの問題が大きいようです。
関連ページ:「すらら うざい」
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」という名称のプランはありませんが、ADHDやASD、LDなどの特性に配慮した設計がされており、通常のコース内でそのままサポートを受けられます。
料金は一般コースと同じで、特別な割引などはない代わりに、どの子にも“フラット”な学習機会を提供することを大切にしています。
個別対応が必要な場合も、すららコーチがフォローしてくれるので、安心して使える設計になっています。
関連ページ:「すらら 発達障害 料金」
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、一定の条件を満たせば、すららでの家庭学習が「出席扱い」として認められることがあります。
すららは文部科学省の出席扱いガイドラインに準拠した教材で、実際に全国の学校や教育委員会との連携実績も多数あります。
ただし、出席扱いになるかどうかは学校長の判断となるため、事前に学校との相談や必要書類の準備が大切です。
コーチや公式サイトのサポートも活用しながら進めていきましょう。
関連ページ:「すらら 不登校 出席扱い」
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは時期によって入会時に使えるキャンペーンコードが配布されることがあります。
キャンペーンコードは、申し込みフォームの所定欄に入力することで適用されます。
割引内容は「初月無料」や「Amazonギフト券プレゼント」などさまざまです。
使用期限や条件がある場合もあるので、必ず事前に公式サイトで最新情報をチェックしてから申し込みましょう。
関連ページ:「すらら キャンペーンコード」
すららの退会方法について教えてください
すららの解約・退会は、基本的に「電話での手続き」が必要です。
メールやマイページからの解約はできないため、すららコール(カスタマーサポート)に直接連絡し、氏名・IDなどの情報を伝えて進める流れになります。
解約希望日までに手続きが完了すれば、以降の料金は発生しません。
なお、解約後に会員情報を完全に削除したい場合は、別途「退会申請」も必要になるので注意してください。
関連ページ:「すらら 退会」
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に必要なのは「入会金」と「毎月の受講料」だけで、追加で教材を買ったり、タブレットを別途購入する必要はありません。
もちろん、すららを使うための端末(パソコン・タブレットなど)は各家庭で用意する必要がありますが、専用端末の販売などは行っていません。
そのため、既にお持ちのタブレットやPCがあれば、追加費用なしですぐに始められるのがメリットです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは基本的に「契約者1名につき1アカウント」となっており、兄弟で一緒に使う場合でも、原則としてそれぞれ個別に契約が必要になります。
ただし、兄弟利用の相談ができることもあるので、状況によっては「2人目割引」や特別な利用方法の提案をしてもらえるケースもあります。
公式サイトまたはサポートセンターですららコールに相談してみるのがおすすめです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースにも「英語」はしっかりと用意されています。
リスニング・リーディング・スピーキングに対応しており、ネイティブ音声を聞いて発音を練習したり、アニメーションで文法を学ぶ内容が充実しています。
英語に初めて触れるお子さんでも無理なく取り組めるように作られているので、小学生のうちから英語に親しみたい方にはぴったりの教材です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの「すららコーチ」は、学習計画の立案から日々の学習フォローまで、幅広くサポートしてくれる専任の学習コンサルタントのような存在です。
子どもの特性や学習履歴に合わせて最適な学習プランを提案してくれたり、つまずきポイントのフォローや励ましの声かけなどもしてくれます。
保護者の相談にも応じてくれるので、親子だけで抱え込まない安心感があるのが特長です。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
「すららってよく聞くけど、他のタブレット教材と何が違うの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
特に不登校のお子さんをサポートしたいご家庭にとっては、「ちゃんと続けられる?」「学校の出席扱いになる?」といったポイントが非常に気になるところですよね。
すららは、ただのタブレット学習教材ではなく、文部科学省のガイドラインに沿った内容や、学習の記録・サポート体制までしっかり整っているのが特長です。
この記事では、スマイルゼミ、チャレンジタッチ、スタディサプリなど、他の人気タブレット教材と比べて、すららが「なぜ不登校の子に選ばれているのか」をわかりやすく解説します。
出席扱いの実績、学習内容、サポート体制などを比較しながら、あなたのお子さんにぴったりの学習環境を選ぶためのヒントをお届けします。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ すららは、不登校のお子さんが自宅で学習を続けながら「出席扱い」として認めてもらえる可能性のある教材です。
文部科学省のガイドラインに沿っており、学習記録の提出やコーチによる学習支援など、出席扱いに必要な条件を満たしやすい仕組みが整っています。
すららは、不登校のお子さんが自宅で学習を続けながら「出席扱い」として認めてもらえる可能性のある教材です。
文部科学省のガイドラインに沿っており、学習記録の提出やコーチによる学習支援など、出席扱いに必要な条件を満たしやすい仕組みが整っています。
ただし、出席扱いは学校長の判断によるため、事前に担任や校長先生への相談が欠かせません。
医師の診断書が必要なケースもあるため、状況に応じた準備が大切です。
また、学習時間や教科のバランス、継続性なども評価のポイントになります。
すららをうまく活用しながら、学校・家庭・コーチの三者で連携をとることで、制度をスムーズに活用できる可能性が高まります。
大切なのは「出席日数を増やすため」ではなく、「お子さんが自分のペースで学びを続けられる環境を整えること」。
その結果として、出席扱いが認められるのであれば、それは大きな安心材料になります。
</p>
ただし、出席扱いは学校長の判断によるため、事前に担任や校長先生への相談が欠かせません。
医師の診断書が必要なケースもあるため、状況に応じた準備が大切です。
また、学習時間や教科のバランス、継続性なども評価のポイントになります。
すららをうまく活用しながら、学校・家庭・コーチの三者で連携をとることで、制度をスムーズに活用できる可能性が高まります。
大切なのは「出席日数を増やすため」ではなく、「お子さんが自分のペースで学びを続けられる環境を整えること」。
その結果として、出席扱いが認められるのであれば、それは大きな安心材料になります。
</p>
関連ページ:「すらら うざい」
