すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
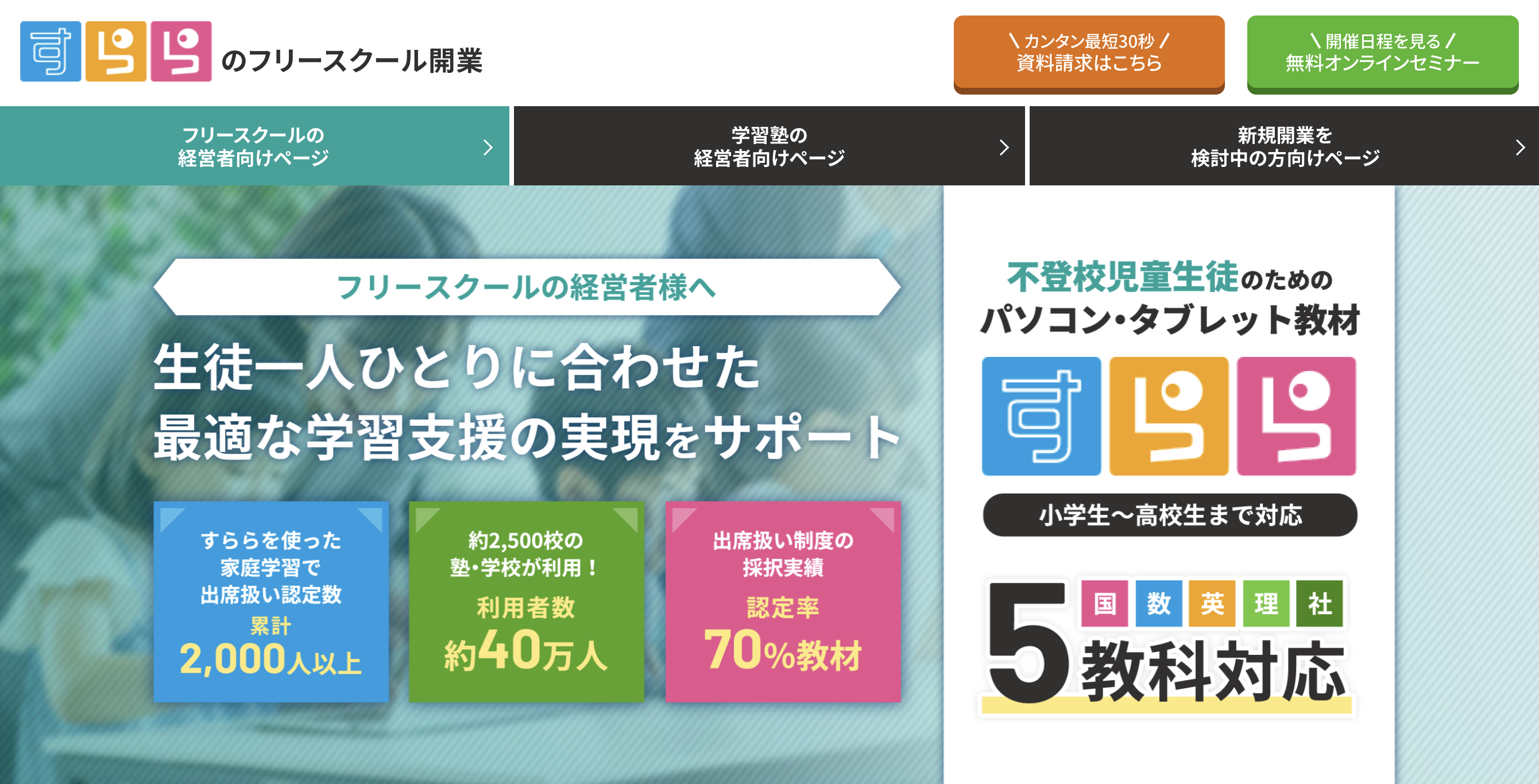
「すららって本当に良いの?」
「なんかうざいって声もあるけど…」そんなふうに感じたこと、ありませんか?
最近よく名前を聞く「すらら」は、無学年式のオンライン学習サービスとして注目されています。
ただ、ネットで検索していると「うざい」といったネガティブなワードが出てくることもありますよね。
でも実際は、使ってみて初めてわかる魅力や、他の教材にはない強みがあるんです。
学習につまずきを感じているお子さんや、個別指導が合わなかった方にとって、「すらら」は新しい可能性をくれるツールです。
今回は、そんな「すらら」がなぜ選ばれているのか、そのおすすめポイントをわかりやすく紹介していきます。
「うざい」と感じる理由や誤解されがちな点にも少しだけ触れながら、本当の良さを一緒に見ていきましょう。
気になっていた方は、この記事を読んで判断材料のひとつにしてみてください。
きっと、今まで見えていなかった一面が見えてくるはずです。
すららのおすすめポイントをまとめました
「すらら」が多くの家庭に選ばれている理由には、いくつかの大きなポイントがあります。
まず、無学年式であることが特に注目されています。
これは、学年にとらわれず、自分の理解度に応じて進められるという仕組みです。
次に、アニメーションや対話形式の授業があることで、子どもたちが飽きずに学習を続けやすいという特徴もあります。
さらに、保護者にとって嬉しいのが、学習の進捗や苦手分野が見えるサポート体制です。
このように、「勉強のつまずきを解消したい」と願う家庭にとって、すららは心強い存在になってくれるんです。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの大きな特長は、学年の枠を超えて学習できる「無学年式」のスタイルです。
一般的な教材のように「この単元は◯年生で習うもの」と決まっていないので、得意な分野は先取りして進めることもできるし、苦手な部分は何度も繰り返してじっくり理解することもできます。
子どもの理解度や個性に合わせた学び方ができるから、置いてけぼりになる心配もありません。
どの学年の子でも、自分に合ったスピードで学べる柔軟さが、すららの強みです。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
学校の進度や学年の枠にとらわれず、子ども自身の理解度にあわせて進められるのがすららの魅力です。
たとえば算数の「わり算」がわからない場合でも、前の学年の「かけ算」までさかのぼって復習することができます。
逆に、もう理解しているところはどんどん先に進んでいいので、無駄な時間を過ごすこともありません。
一人ひとり違う「わかるまでの時間」に寄り添ってくれるから、子どもがストレスを感じにくいのも嬉しいポイントです。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
すららでは、テストの結果や理解度に応じて自動でおすすめの単元が提示されるので、「どこから勉強すればいいかわからない」という迷いがありません。
得意なところはスムーズに先に進めて、難しいと感じる部分は復習に戻れる仕組みになっているので、効率よく学べます。
自分の力で学ぶ感覚が身につくうえ、苦手意識も自然と減っていきます。
つまずいた時も「今どこがわからないのか」がはっきり見えるから、対処しやすいんです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの授業は、ただの動画視聴ではありません。
アニメーションのキャラクターが「先生」となって、子どもと対話しながら授業を進めてくれます。
聞かれて答える、考えて選ぶというインタラクティブな要素があるので、受け身の学習にならず、自分で考えるクセが自然とつきます。
見た目の楽しさだけでなく、理解しやすさにもしっかり配慮されているのが、すららの強さです。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららでは、キャラクターが授業を担当してくれるので、まるで家庭教師がついているような感覚で学べます。
ただ映像を見るだけでなく、キャラから質問されて答えたり、選択肢を選んだりする対話形式なので、子どもが飽きずに集中しやすいのが特徴です。
感情豊かなアニメの演出が、子どもの興味をひきつけてくれます。
静かな教材では集中できないお子さんにもぴったりの工夫です。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
苦手意識が出やすい算数や理科なども、すららなら視覚的に理解しやすく工夫されています。
図やグラフ、アニメーションの動きなどが使われていて、文章だけではわかりづらい概念も直感的に理解できます。
抽象的な内容も、目に見える形で伝えてくれるので、「ああ、こういうことだったのか」と納得しながら学べます。
言葉で説明されてもピンとこなかった内容が、自然と頭に入ってくるんです。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
授業を進めるとキャラクターが「よくできたね!」「すごい!」と声をかけてくれるので、子どもは自然とモチベーションが上がります。
一方的な学習ではなく、褒められることで達成感を感じながら続けられるのがポイントです。
「続けることが難しい」「飽きっぽい」と感じるお子さんでも、キャラとのやり取りが楽しみになって、学習習慣が身についていきます。
「またやりたい」と思わせてくれる仕組みが、すららには詰まっています。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
家庭学習の最大の悩みといえば、親のサポート負担ですよね。
すららでは、「すららコーチ」と呼ばれる専門スタッフが付き、学習の流れや計画、フォローまでを担当してくれます。
保護者はすべてを管理する必要がなく、見守るだけでOKというのが大きなメリットです。
忙しい家庭でも安心して続けられる環境が整っています。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
学習の開始前に、すららコーチが子どもの状況をヒアリングし、それをもとに個別の学習計画を作成してくれます。
進捗に応じて計画を調整したり、つまずきのサインを見つけてサポートしたりと、きめ細かい対応が魅力です。
子ども自身だけでなく、親にも安心を届けてくれる存在になっています。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、子どもの性格や得意・不得意、学習スタイルにあわせて最適なスケジュールを提案してくれます。
たとえば集中力が続かない子には短時間×高頻度の構成にしたり、得意分野はやや多めに組んであげたりと、本当に「その子に合った計画」を作ってくれます。
画一的な教材とは違い、一人ひとりの背景に寄り添ってくれる柔軟さが安心です。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
学習中に出てきた疑問や悩みは、すららコーチに直接相談できる仕組みになっています。
子どもも親も「何かあったときは相談できる」という安心感があり、学習が止まってしまうリスクも減らせます。
「全部親が管理しなきゃ」と思う必要がないので、共働き家庭や多忙なご家庭でも無理なく続けられます。
保護者のストレスが減ることも、すららの大きな価値のひとつです。
見守るだけでOK
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、ただの学習教材ではなく、学習に不安を抱える子どもたちにも寄り添う設計になっています。
発達障害や不登校といった背景を持つお子さんにとって、「できない」「ついていけない」という不安はとても大きな壁です。
でも、すららはその壁を少しずつ壊していけるような、やさしい工夫がたくさん詰まっています。
子ども一人ひとりの特性に合わせて、無理なく学べる柔軟なシステムが整っているから、誰にとっても安心して取り組める学習環境になっているんです。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、ただのオンライン教材ではありません。
実は「文部科学大臣賞」を受賞しているほど、社会的にも信頼されている学習支援ツールです。
この賞は、教育現場での実績や有効性が高く評価された教材に贈られるものなので、それだけでも安心感がありますよね。
家庭での学習をサポートする教材の中でも、ここまで評価されているものは珍しく、教育関係者からの支持も厚いです。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
すららは、ADHDや学習障害などを持つお子さんにも配慮された設計になっています。
たとえば集中力が切れやすい子には短いセッションで進められるよう工夫されていたり、説明が視覚や聴覚の両方に対応していたりと、多様な子どもの特性に対応しています。
自分のペースで繰り返し学べる点も、発達に特性がある子どもたちにとって大きな安心材料です。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
すららは、自宅から安心して学べる教材なので、不登校の子どもたちにもとても相性がいいです。
学校の授業に遅れてしまった場合でも、無学年式で自分のわかるところからスタートできるため、焦らずに取り組めます。
「いきなり難しい内容が出てくる」ということがないので、学び直しや復習にもぴったりです。
不登校の子でも、自分のペースを大切にしながら勉強が続けられる仕組みになっています。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららでは、学習中のつまずきをAIがしっかり分析してくれます。
間違えた問題や理解があいまいな箇所を自動で検出し、その内容に合わせた問題を出してくれるので、効率よく弱点を補強できます。
「何がわからないのか」を自分で把握するのは意外と難しいですが、すららならAIがその役割を担ってくれるので安心です。
苦手をそのままにせず、次に活かせるよう導いてくれる機能が頼もしいです。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
どれだけ勉強しても「成果が見えない」と、モチベーションは下がってしまいますよね。
すららには、学習内容の定着度をその場で確認できるテスト機能や、AIによるリアルタイム分析がついています。
テストで間違えた問題にすぐ対応できたり、学習の進み具合を客観的に見られたりと、見える化がしっかりしているんです。
保護者も安心できるだけでなく、子ども自身が「できた」という実感を持ちやすいのも魅力です。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららのテスト機能では、問題に間違えたときすぐにフィードバックされる仕組みがあります。
正解を見て終わりではなく、なぜ間違えたのか、どこを見直せばよいのかまで丁寧に教えてくれるので、次につながります。
この「すぐに見直せる」ことが、理解の深まりと定着に効果的です。
小さなテストでも確実に成果が積み上がっていく感覚が味わえます。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
すららのAI機能は、ただ結果を記録するだけでなく、学習内容の定着度を診断してくれます。
理解が不十分な単元を自動で判断し、ピンポイントで補強問題を出してくれるのが特徴です。
苦手を苦手のままにしない仕組みがあるので、自然と自信もついてきます。
学習効率を上げたいと考える家庭にはぴったりのサポートです。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
子どもがどこを勉強していて、何が得意・不得意なのか。
すららでは、そうした情報が保護者にも定期的にレポートとして配信されます。
わざわざ学習内容を全部チェックしなくても、レポートを見るだけで把握できるから、忙しい親にとってはとても助かります。
子どもの成長を一緒に感じられる安心感もあります。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
英語学習において大切な「聞く」「読む」「話す」の3つのスキルを、すららではバランスよく伸ばすことができます。
学校の授業や参考書では補いにくいスピーキングやリスニングも、すららなら実践的に学べます。
アニメーションを通じた解説もあるので、初めて英語を学ぶ子でも安心して取り組めるんです。
英語に苦手意識がある子にも優しい設計になっています。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
すららでは、英語のリスニングをネイティブスピーカーの発音で学ぶことができます。
機械音声ではなく、自然な英語の発音が聞けるので、耳が英語に慣れやすくなります。
英語のリズムやイントネーションに親しむことで、リスニングの力が自然とついていくんです。
試験対策にも役立つ本物の英語に触れられるのが魅力です。
音読チェックでスピーキング練習ができる
すららには、英語のスピーキングを練習できる音読チェック機能もあります。
自分の声を録音して、ネイティブの音声と比較しながら発音の練習ができるため、ただ読むだけの学習では終わりません。
実際に口に出すことで、英語のリズムが身につきやすくなります。
話す練習を重ねることで、英語への抵抗もどんどん減っていきます。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
英単語や文法などの細かい知識も、すららではアニメーションを使ってわかりやすく解説してくれます。
意味だけでなく、使い方や例文まで丁寧に紹介されるので、ただ覚えるだけでなく「使える英語」が身につきます。
英検などの資格試験を目指す子にも、しっかり対応できる内容になっています。
繰り返し学習しやすい構成なので、試験対策にもぴったりです。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、1人ずつ契約する必要がありません。
1つのアカウントで兄弟一緒に使えるうえ、科目の追加も自由にできるため、コストパフォーマンスの良さが抜群です。
「子どもが2人以上いると料金がかさむ…」という家庭でも、安心して導入できる仕組みになっています。
柔軟な設計だからこそ、いろんな家庭にフィットするんです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららでは、1つの契約で複数の子どもが同時に利用できます。
たとえば兄と妹で別々の学年だったとしても、追加料金なしでそれぞれのペースで学習できるんです。
兄弟が多い家庭にとっては大きなメリットで、経済的にも助かります。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
学年が離れている兄弟でも、同じすらら内でそれぞれの学習ができるので、家庭内の管理もシンプルです。
教材をいくつも揃える必要がなく、手間もお金も節約できます。
無学年式だからこそ、異なる学年の兄妹でも問題なく使えるのが嬉しいポイントです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららでは、必要な科目だけを選んで追加できるので、不要な教科にお金をかける心配がありません。
「英語だけ強化したい」「数学だけ先取りしたい」など、家庭のニーズに合わせて柔軟に選べます。
必要な分だけ学べる仕組みなので、コストも時間も無駄が出にくいです。
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
「すららって他の教材とどう違うの?」
そんなふうに疑問に感じている方も多いと思います。
最近では、家庭用のタブレット教材がたくさん登場していて、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。
その中でも「すらら」は、一部では「うざい」といった声がある一方で、実際に利用している家庭からは高く評価されている教材でもあります。
ポイントは、ただのデジタル教材ではなく、子どもの個性や状況に合わせたサポート体制がしっかり整っているところ。
特に、不登校や発達障害に対応している点、学年を超えて柔軟に学べる無学年式、さらにはプロの学習コーチの存在など、他の教材ではなかなか見られない特徴が詰まっています。
今回はそんな「すらら」ならではのメリットについて、具体的にご紹介していきます。
今タブレット教材を検討中の方も、「他とは違う視点」で見てもらえるきっかけになるはずです。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
タブレット教材って、子ども任せになりがちで、続けられるか不安になることありますよね。
すららはそこが大きく違います。
プロの学習コーチが子どもの進捗を見守りながら、必要に応じてアドバイスをくれるサポート体制があるんです。
学習の途中でつまずいても、ひとりで悩ませることなく、しっかり支えてくれる仕組みが整っています。
親も無理にサポートに入らずに済むので、家庭全体の負担も軽くなります。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららコーチは、単に「アドバイス役」ではありません。
子どもの学習履歴やテスト結果を見ながら、どこが得意でどこが苦手かを把握して、必要なサポートをタイムリーに届けてくれます。
つまずきが見つかれば、すぐに適した単元を提案してくれるので、苦手が広がる前に対応できるのが安心です。
プロの目線で子どもの成長を見守ってくれるのは、とても心強い存在です。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
学習計画を立てるのって意外と大変ですが、すららではこの部分もおまかせできます。
すららコーチが、子どもの性格やライフスタイルに合わせて、無理のないスケジュールを作成してくれます。
「週3回」「30分ずつ」といった細かいプランも組めるので、家庭に合ったペースで進められます。
計画があるだけで子どもも取り組みやすく、学習の習慣化にもつながります。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
他のタブレット教材とすららの大きな違いは、「どんな子にも寄り添える教材」であるということです。
不登校や発達障害のある子は、学習に対して不安や抵抗感を抱きやすいですが、すららはそうした子どもたちが安心して学べるように設計されています。
社会的な評価も高く、実際に学校での出席扱いになるケースもあるほど信頼されているんです。
学びの機会を逃さず、子どものペースを尊重した学習ができるのが、すららの強みです。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省の推薦を受けて、実際に学校教育の一環として使われている実績があります。
これは「家庭での学習でも十分な成果が期待できる教材」として、教育現場から評価されている証です。
不登校の子どもにとっては、学校に行かずとも安心して学べる環境があるというのはとても大切なこと。
公式な実績があるからこそ、保護者も安心して選べる教材になっています。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを使っての学習は、一定の条件を満たせば「出席扱い」になることがあります。
これは、不登校の子どもが学びを継続できる手段として、学校側も認めているということです。
出席日数や学力の面での心配が減ることで、子どもも親も大きな安心感を得られます。
学校との連携が取りやすい教材という点も、すららの信頼度を高めています。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
すららでは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)など、発達に特性のある子ども向けに設計されたカリキュラムやサポートが整っています。
テンポの速さや説明の方法、内容の出し方などが工夫されていて、特性を持つ子でも取り組みやすいように配慮されています。
一人ひとりの違いに対応できる教材だからこそ、安心して使えるんです。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
「すららってどの学年向け?」と思われるかもしれませんが、実はすららには学年という概念があまりありません。
理解度に応じて、何年生の内容であっても自由に進めたり戻ったりできる、いわゆる「無学年式」スタイルが採用されているんです。
これは、特に発達に特性がある子や、不登校で一時的に学習が抜けてしまった子にとって、大きなメリットになります。
自分のペースを大事にしながら、学力を着実に積み上げていけるのがすららの魅力です。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
すららの教材は、教科ごとに単元が整理されていて、学年に関係なく学びたい単元にすぐアクセスできます。
たとえば「小学4年生だけど2年生の計算を復習したい」ということも可能ですし、「得意な英語は中学生レベルに挑戦したい」ということもできます。
自分に合ったタイミングで、理解できるまで何度でも繰り返せるのが大きな強みです。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達に特性がある子は、前の単元でつまずいたまま新しい内容に進むと、ますます混乱してしまうことがあります。
でもすららなら、わからないところは何度でも復習できるので、しっかり理解してから次に進めるんです。
学びの基礎を固めることで、苦手意識が減り、自信を持って学習できるようになります。
マイペースな学び方ができるからこそ、すららは特性を持つ子どもにもやさしい教材なんです。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららの最大の特長のひとつが、AIによる診断と人間のコーチによるサポートが組み合わさっている点です。
AIの力だけに頼らず、子どもの学習状況を「人の目」で確認して、必要に応じた調整をしてくれるのがすららならではの安心感です。
完全自動でも、完全人力でもなく、AIと人のいいとこどりをした学習設計だからこそ、子ども一人ひとりにピッタリの学びが実現できるんです。
細やかな学習支援がほしい家庭にはとても心強い仕組みです。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
すららでは、学習の診断をAIが担当し、その結果をもとに人間の「すららコーチ」がサポートを行います。
AIは、理解度やミスの傾向をもとに苦手を見つけ出し、最適な復習問題を提示してくれます。
その上で、コーチが子どもに合わせたアドバイスを届けてくれるから、より実践的な学習ができるんです。
このWサポートは、他の家庭学習教材にはなかなか見られないすらら独自の強みです。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIはデータに強くても、子どもの気持ちや生活リズムまで読み取ることはできませんよね。
すららのコーチは、学習状況の変化や子どもの性格もふまえて、スケジュールや目標を細かく調整してくれます。
調子が悪い時期には無理のない学習に切り替えるなど、柔軟な対応ができるからこそ、継続しやすいんです。
学力だけでなく「気持ち」にも寄り添うサポートがあるのがすららの良さです。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
「タブレット学習だと記述力が育たないんじゃない?」そんな不安を持つ方もいますよね。
でも、すららはその点にもちゃんと対応しています。
すららには、記述問題に特化したカリキュラムが組まれていて、考えて書く力や、順序立てて説明する力を育てる内容が含まれているんです。
デジタルで完結するのに、紙の教材に負けない学びができるのがすららの特徴です。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららでは、ただ正解を選ぶだけの問題ではなく、「自分の言葉で答える」記述問題が取り入れられています。
子どもが自分で考え、順序立てて説明する練習ができるため、論理的思考力や表現力も自然と育っていきます。
この力は、テストだけでなく将来にも役立つスキル。
だからこそ、すららのように「書く力」を意識した設計がされている教材は貴重なんです。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
読解力と記述力をセットで学べる教材は、意外と少ないものです。
すららは、文章を読んで理解するだけでなく、それに対する考えを自分の言葉で表現する力をつけるトレーニングができます。
しかもすべてタブレット上で完結するので、紙の用意や提出も不要。
手軽なのにしっかりと力がつく教材として、特に文章表現が苦手な子にもおすすめです。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
一度教材をやめてしまうと、再開するのが面倒になってしまうことってありますよね。
でもすららは、その点も柔軟に対応できる仕組みになっています。
学習の進捗や理解度の履歴がきちんと保存されているので、どこまでやったかがすぐにわかり、再スタートもスムーズです。
特に体調や気分の波がある子どもにとっては、「いつでも戻れる」という安心感が続ける力になります。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
途中で学習を休んでも、再開するときは前の状態からすぐに始められます。
ログインするだけで、前回どこまでやっていたか、どこを復習すればいいかがすぐにわかるようになっているんです。
この気軽さがあることで、「また今日から頑張ろう」と思いやすくなります。
毎日続けることが難しいご家庭でも安心して使えます。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
子どもによっては、学習のモチベーションや集中力に波があることも多いです。
特に発達に特性がある子は、体調や気分に合わせて無理なく進められる環境が必要ですよね。
すららは途中で休んでも、焦らず戻れるシステムがあるから、子どもも安心して取り組めます。
休んだことを責めず、戻ってきたことを歓迎してくれる雰囲気が大切です。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、家庭での学習ツールという枠を超えて、教育機関とも連携して活用されています。
その実績は、出席扱いとして認められる学校が多いことや、教育委員会との協力体制があることからもわかります。
家庭学習だけでなく、公的なサポートとの連携を重視したい方にとって、すららはとても信頼できる選択肢なんです。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
不登校の子どもがすららで学習していることを、出席として認める学校が増えています。
これは文部科学省の方針にも沿ったもので、すららが公式に認められた教材であることの証です。
出席日数に不安を抱えるご家庭でも、安心して学びを継続できます。
子どもが自信を取り戻すきっかけにもなります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、家庭だけでなく、学校現場や医療機関とも連携して活用されている実績があります。
不登校支援として導入されているケースも多く、学びを止めずにサポートを受けられる教材として高く評価されています。
子どもの状況に合わせて多方面から支える仕組みがあるからこそ、信頼して使える教材なんです。
【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは多くの家庭に選ばれている人気の教材ですが、一部では「うざい」と感じている人の声も見られます。
SNSや口コミサイトでは、勧誘がしつこい、キャラクターが子どもっぽい、サポートが過剰など、気になる点を挙げている投稿もあります。
ですが、こうしたネガティブな印象の多くは、「すららが合わなかった人の視点」で語られていることが多いんです。
どんな教材にも合う・合わないはありますよね。
この記事では、「うざい」と言われる原因をひとつずつ紐解きながら、すららのデメリットと向き合ってみたいと思います。
そのうえで、「自分の子どもに合っているかどうか」を判断する参考にしてもらえたら嬉しいです。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららでは、学習がきちんと進んでいるかを見守るために、コーチからの連絡が届くことがあります。
このサポートは心強い反面、「自分のペースでやりたい」と思っている子や保護者にとっては、少し頻繁に感じることもあるようです。
特に自主性が強い子には「干渉されている」と感じることがあるかもしれません。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららは手厚いサポートが魅力ですが、誰にでも合うわけではありません。
「見守ってほしい」よりも「放っておいてほしい」と思っている子には、逆にストレスになることもあります。
干渉されているような感覚が強いと、やる気を失ってしまうこともあるので、その子の性格との相性は大切です。
サポートの有無を選べるようになると、さらに使いやすくなるかもしれません。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららではAIやコーチが学習計画を立ててくれるため、計画通りに進まないと「やらなきゃ」というプレッシャーが生まれることもあります。
この「やらされている感」が強くなりすぎると、かえって学習意欲が下がることがあります。
特にストレスに敏感な子は注意が必要です。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
AIによる学習計画は便利ですが、時には「自分で選びたい」と思う子にとっては窮屈に感じることもあります。
特に「今日は気分が乗らない」といったときに、計画に縛られていると感じてしまうと、プレッシャーが大きくなってしまうかもしれません。
もう少し自由度が高いと、より続けやすくなると感じる家庭もあります。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららは小学生〜中学生向けに作られていることもあり、ナビゲーションキャラクターが親しみやすいデザインになっています。
ですが、思春期の子や高学年になると「子どもっぽくてうざい」と感じるケースもあるようです。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
キャラクターの演出や話し方は、低学年の子には楽しいと感じられる一方で、中学生以上になると「くどい」「うるさい」と思ってしまうこともあります。
特に思春期に差しかかったタイミングでは、こうしたキャラクター性に敏感になる子も多いです。
年齢や好みに応じて、キャラクターのON/OFFが選べるともっと使いやすくなるかもしれません。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららを調べていると、「問い合わせをしたあとに何度も連絡が来た」という声も見かけます。
このような対応を「丁寧」と感じるか「しつこい」と感じるかは人それぞれですが、SNSでは後者の声も目立つことがあります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
体験申し込み後や資料請求のあとに複数回連絡が来ることで、「押し売りみたい」と感じてしまう人もいます。
親切なサポートのつもりでも、受け取る側にとっては負担になることもあるので、この点は好みが分かれるところです。
最初から「連絡の頻度が選べる」ようにしておくと、もっと印象がよくなるかもしれません。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは、他の家庭学習サービスに比べてやや高めの価格帯にあります。
その分サポートや機能が充実しているのですが、子どもがうまく活用できない場合、「この金額の価値があるのかな?」と疑問に思う家庭もあるようです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
どんなに良い教材でも、子どもが主体的に取り組まなければ効果は感じにくいものです。
特に、まだ学習習慣がついていない段階だと「放っておくと全然やらない」という悩みも出てきます。
この状態が続くと「料金が高いのに成果が見えない」と感じる保護者も少なくありません。
最初の導入サポートが鍵になる場面もあるので、初期フォローの工夫が求められるかもしれません。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
すららが気になっているけど、「ちょっと高そう…」という印象を持っている方、多いのではないでしょうか?
家庭用のタブレット教材と比べて、すららの料金は少し上の価格帯にあるのは確かです。
でもそのぶん、学習コーチによる個別サポートや、無学年式、AI診断など、他にはない魅力がしっかり詰まっているんです。
「高い=ムダ」と感じるか、「高いけど価値がある」と思えるかは、サポート内容や学習スタイルとの相性次第。
この記事では、すららの具体的な料金プランを詳しく紹介しながら、「なぜこの価格なのか」についてもわかりやすくお伝えします。
どこまでが基本料金なのか、どのタイミングで支払いが発生するのかなど、気になる点をしっかり押さえて、安心して検討できる材料にしてくださいね。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを始めるにあたって、まず発生するのが「入学金」です。
この費用は初回のみで、コースによって金額が異なる場合もありますが、おおむね7,000円〜11,000円程度が目安となっています。
タブレット自体は別途購入する必要はなく、PCやタブレット端末が自宅にあればそのまま使えるので、機材費の負担が少ないのは安心ポイントです。
入学金は一度だけの支払いなので、初期費用としてあらかじめ準備しておくとスムーズにスタートできます。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの基本プランのひとつが、3教科(国語・数学・英語)のセットです。
このプランは、多くの家庭が最初に選びやすいバランス型で、基礎教科を中心に学びたいお子さんに向いています。
月額制なので、自分のペースで学習を継続しやすく、料金体系も明確です。
料金は支払い方法によって少し変わってくるので、次で詳しく紹介します。
毎月支払いコースの料金
毎月支払いで利用する場合、3教科コースの料金は月々およそ8,800円〜10,978円前後となっています。
学年や受講コースによって若干変動がありますが、おおよその相場はこの範囲です。
他の通信教材と比べると少し高めに見えるかもしれませんが、個別対応のサポートがあることを考えると、納得しやすい価格と言えるかもしれません。 払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
すららでは、4ヵ月以上続ける前提で申し込むと、ややお得な料金プランを選ぶこともできます。
3教科プランでの4ヵ月継続コースは、月額7,000円台になるケースもあります。
ただしこの場合は中途解約ができない期間があるため、「まず続けてみたい」という方に向いています。
長く使う予定がある方には、コスパが良い選択です。継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
理科と社会を加えた4教科コースは、より幅広く学びたいお子さん向けのプランです。
このプランの月額料金は、約9,900円〜12,100円あたりとなっていて、こちらも支払い方法や学年によって若干前後します。
理社が加わる分、定期テスト対策や受験準備を意識した学習にも対応しやすくなっています。
内容のボリュームが増えるわりに、大きく料金が上がらない点はうれしいですね。月額料金について
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
フルセットの5教科コースは、すららの中でももっとも内容が充実したプランです。
受験対策はもちろん、幅広い分野を一貫して学びたい家庭に人気があります。
英語を含めた5教科のトータルサポートが受けられるので、総合力を高めたい方にぴったりの選択です。
料金については、次の見出しで支払い方法ごとの金額をご紹介します。
毎月支払いコースの料金
5教科プランを毎月支払いで契約した場合、月額およそ10,978円〜13,200円程度となることが多いです。
この中にはコーチングサポートや進捗管理などのサービスも含まれており、ただ教材を使うだけでなく、学習環境全体が整うイメージです。
「少し高いけど、それだけの内容がある」と感じるご家庭も多いです。払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
4ヵ月以上の継続コースでは、5教科プランの月額が9,800円台におさまることもあります。
長期でじっくり取り組みたい家庭にはとてもお得で、月ごとの支払いよりもコストを抑えられます。
ただし、途中解約は原則できないため、まず体験やお試し期間での相性チェックをしてからの申し込みが安心です。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららって本当に効果あるの?って気になりますよね。
特に家庭用タブレット教材は「やるだけで終わってしまいそう」「成果が見えにくそう」と不安に感じる方も多いはずです。
でも実は、すららにはAI診断や個別サポートがあることで、ただやみくもに勉強するのではなく、「成果につながる学習」ができる仕組みが整っています。
今回はその中でも、国語・数学・英語の3教科コースに絞って、「実際どんな勉強効果があるの?」という視点から解説していきます。
特に中学生の内申点対策や、定期テストでの点数アップを目指している家庭にとっては、この3教科をどう押さえるかがとても大切。
すららがどうやって効率よく学びをサポートしてくれるのか、具体的なポイントを見ていきましょう。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
3教科コースは、基礎学力の土台をしっかり固めたい家庭にぴったりのコースです。
国語・数学・英語は、どの学年でも重要度が高く、定期テストや受験の得点源にもなりやすい教科です。
すららでは、この3教科を「無学年式×AI×個別フォロー」で学べるので、ただ解くだけでは終わらない理解が深まる学習ができます。
勉強時間が限られている子にも効果が出やすい設計になっているので、忙しい子でも取り組みやすい内容です。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららでは、基礎となる知識を短時間でしっかり定着させる工夫が盛り込まれています。
「単に覚える」のではなく、「なぜそうなるのか」を対話形式で理解しながら進めることで、頭に残りやすくなるんです。
特に数学や英語の文法など、積み上げ型の学習においては、土台の理解がものを言います。
だからこそ、すららの基礎固めが早く終わることは、応用力を育てるうえでもとても大きなメリットなんです。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららでは、一問一答のような形式だけでなく、「まずやってみる→なぜそうなるかを知る→似た問題で試す」というステップを踏んで進めていきます。
これにより、ただ正解するだけでなく、自分の頭で理解する力が自然と身についていきます。
1日30分でも集中して取り組めば、短時間で確実に「わかった」という実感が持てる構成です。
無駄のない流れが、忙しい子どもにもピッタリなんです。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって、国語・数学・英語は定期テストの配点も高く、内申点にも大きく関わってきますよね。
すららでは、テスト対策用の復習モードや、苦手克服に特化した問題も用意されているため、「点を上げること」に直結する学びができます。
AIが弱点を分析し、自動で問題を出してくれるので、効率的に成果を出すことができるんです。
「勉強はしてるのに点数が伸びない」と悩むご家庭にもおすすめの内容です。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
理科や社会も合わせて学びたい方に選ばれているのが、すららの4教科コースです。
主要3教科に加えて、理解しにくい理科や暗記が多い社会も含まれているため、テスト対策としての総合力が高まる構成になっています。
すららでは、視覚的な説明や繰り返し演習、AIによる理解度チェックが組み合わされているため、ただ読むだけ、聞くだけの学習よりも記憶に残りやすくなります。
時間をかけすぎずに成果が見えるという点で、忙しい家庭にも嬉しいコースです。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会の内容は、覚えたつもりでもすぐに忘れてしまうことが多いですよね。
すららでは、重要ポイントを繰り返し学べる設計になっていて、さらに確認テストもその都度行えるので、自然と知識が定着していきます。
一度学んだ内容を何度でも復習できる仕組みがあるので、苦手な単元も無理なく克服できるんです。
暗記が苦手な子にもおすすめの学習スタイルです。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららの理社コンテンツは、単元ごとの重要ポイントがコンパクトにまとめられているので、効率よく勉強できます。
全てを網羅するのではなく、「ここを押さえておけば大丈夫」という要点に絞っているから、時間をかけなくても成果につながりやすいんです。
特に試験直前の復習や、苦手克服に集中したい時にぴったりの進め方です。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
学校や塾では時間の制約もあり、すべての内容を丁寧に復習するのは難しいですよね。
すららは、個々の理解度に応じて「必要なところだけ集中して学ぶ」ことができるので、短時間でもテスト対策がしやすい構成になっています。
通塾時間がないぶん、自分のタイミングで学べるのも強みです。
時間効率を重視したい家庭にとって、すららの4教科コースはかなり有力な選択肢になります。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
5教科すべてを網羅したすららのフルコースは、中学生に特に人気のあるプランです。
高校受験を意識したとき、どの教科もバランスよく学習できることが内申点アップや志望校合格に直結するので、このコースを選ぶ家庭も増えています。
AI分析で弱点を自動抽出してくれるだけでなく、プロのコーチがその結果をふまえて計画を調整してくれるので、学習効率が非常に高いのもポイントです。
時間あたりの成果を実感しやすい設計になっているので、「結果を出したい」という目的にはぴったりです。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
内申点は主要5教科すべてが対象になるため、「どれかが苦手」という状態だと成績に大きく影響します。
すららの5教科コースでは、どの教科も同じように重点的に扱うことができるので、成績全体の底上げに効果的です。
得意・不得意の偏りをなくしたい方には、とても相性の良い学習スタイルです。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
すららで身につく力は、日々の勉強だけでなく、模試や入試問題にも応用できる力です。
特に5教科すべてを学ぶことで、教科をまたいだ複合問題にも対応しやすくなり、実践的な力がしっかり育ちます。
受験を意識しているご家庭には、必要な力を効率よく鍛える手段としてとてもおすすめです。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららでは、各教科ごとの成績や学習状況をAIがしっかりチェックし、自動で対策問題を出してくれます。
5教科すべてに対してこの機能が使えるため、苦手がそのまま放置されることがありません。
コーチとAIが連携して、苦手の克服や得点力アップに向けた計画を調整してくれるので、効率よく成果につながるんです。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
SNSや口コミでは、「塾より短時間で理解できた」「やった分だけ効果を感じやすい」といった声も多く見られます。
自分のペースで進められるからこそ、集中しやすく、短時間でも密度の高い学習ができるのがすららの強みです。
忙しい子や、複数教科を効率よく伸ばしたい子にとっては、時間対効果の高さが魅力になります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
発達障害や不登校の子どもにとって、「安心して学べる場所」があることって、本当に大事ですよね。
学校の教室では周囲の視線が気になったり、授業のスピードについていけなかったり…。
そういった不安を抱えている子どもにとって、家庭で自分のペースで学べる教材は、学びの自信を育てる大きな支えになります。
すららは、発達障害や不登校の子にも安心して使ってもらえるよう、教材設計そのものがやさしく、使いやすく工夫されています。
ただ「わかりやすい」だけでなく、子どもの特性や学習スタイルに合わせて学べる柔軟さがあることが、何よりの安心材料なんです。
今回は、すららがどんなふうに発達障害や不登校に寄り添っているのか、具体的な理由をひとつずつ紹介していきます。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららは無学年式の教材なので、「この学年の内容をこの時期にやらなきゃいけない」というプレッシャーがありません。
理解できていればどんどん先に進んでもいいし、つまずいたら前の単元に戻って何度もやり直してもOK。
学校の進度に合わせる必要がないから、自分に合ったペースで無理なく学習を続けられます。
ストレスなく進められる環境は、特性のある子にとってとても大切です。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
学校の授業は、どうしても全員が同じスピードで進むもの。
でも、発達に特性がある子は「ゆっくり理解したい」こともあれば、「得意な分野はどんどん進みたい」ということもありますよね。
すららは、こうした一人ひとりの違いに合わせて学べるので、「ついていけない」「もう知ってるのに退屈」といったストレスがありません。
マイペースに学べることで、自信を持って取り組むことができます。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
集中力に波があるADHDタイプの子には、「調子のいいときに一気に進める」スタイルがぴったり。
逆に、決まったリズムで物事を進めるのが得意なASDタイプの子には、「毎日同じ時間・同じ内容」で進める方が安心ですよね。
すららは、どちらのタイプにも対応できる柔軟な教材なので、子どもの特性に合わせたスタイルで取り組むことができます。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
先生やクラスメイトの前で手を挙げたり、間違えることに不安を感じたり…。
人との関わりがあると、学習以前に「気疲れ」してしまう子もいますよね。
すららは、対面ではなくキャラクターとのやり取り中心なので、そういった緊張を感じることなく、安心して学習に集中できる環境が整っています。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららでは、アニメーションのキャラクターが先生の代わりに教えてくれます。
明るく、やさしい声で話しかけてくれるので、子どももリラックスしながら学習できます。
問題に間違えても、叱られたり、冷たい態度をとられたりすることがないので、「間違えても大丈夫」と思える安心感があります。
この「安心して間違えられる環境」は、学習への自信につながっていきます。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
人と直接話すことに不安がある子にとって、すららはとても心地よい学習環境になります。
誰かと話さなくても、やさしい声で進めてくれるキャラクターと一緒に学ぶことができるので、プレッシャーや緊張を感じることがありません。
だからこそ、学校では見られなかったような集中力や学習意欲が引き出されることもあるんです。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは「特別な子のための教材」ではなく、「誰にとっても学びやすい教材」として設計されています。
これが、発達に特性のある子にとって結果的にぴったり合っているんです。
視覚・聴覚のバランス、説明のスピード、文字の見やすさなど、細かい部分まで配慮されているから、ストレスなく集中しやすくなっています。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららは、年齢や特性に関わらず、誰でも学べるように作られた「ユニバーサルデザイン教材」です。
言葉の使い方、表示の仕方、説明の順序など、すべてにおいて「わかりやすさ」を最優先に設計されています。
だからこそ、「わからないまま進む」ということが起こりにくいんです。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
文字を読むのが苦手なディスレクシアの子や、言葉の理解に時間がかかるASDの子にとって、情報の伝え方はとても大切ですよね。
すららは、読み上げ機能やアニメーションによる補助があるので、文字情報だけに頼らずに学べる仕組みが整っています。
内容を「目でも耳でも」理解できるから、無理なく取り組めるんです。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
人によって、視覚からの情報が得意な子もいれば、聴覚からの情報の方が理解しやすい子もいますよね。
すららは、映像と音声の両方で学習を進められるので、どちらのタイプの子にも対応しやすい設計です。
理解のスタイルに合わせた学習ができるから、学びがスムーズに進みます。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららでは、音声のスピードを自分で調整できる機能もついています。
「早口だと理解が追いつかない」「逆にゆっくりすぎると集中が切れる」といった悩みにも対応できるんです。
その日の気分や集中力に合わせて、快適なスピードで学習できる柔軟さは、特性のある子にとってとても助かります。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
子どもが勉強を嫌いになる理由のひとつに、「間違えると怒られる」「恥ずかしい」と感じる経験があります。
特に発達に特性がある子は、「間違えること=ダメなこと」と思い込みやすく、自己肯定感が下がりやすい傾向があります。
すららは、そういった不安やネガティブな感情が起きにくいように、教材設計の段階から丁寧に配慮されています。
「間違えても大丈夫」と思える環境が、学びを前向きにしてくれるんです。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららは、間違ったときに「なんで間違えたの?」と責めるのではなく、「どうしてそうなるか」をやさしく解説してくれます。
そのため、子どもは怒られたと感じず、むしろ「なるほど」と納得しながら理解を深めることができます。
正解だけにこだわらず、プロセスを大切にしてくれるので、自分に自信を持ちやすくなるのが大きな特長です。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
教室では、まわりの目が気になって手を挙げられないこともありますよね。
でもすららなら、自分だけの空間で誰にも見られずに学べるので、「間違えても恥ずかしくない」んです。
「できない自分」を見せなくていいから、素直にチャレンジできるようになります。
失敗を恐れずに学べる環境って、実はとても貴重なんです。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
勉強が苦手な子でも、「楽しい」と思える仕組みがあると、自然とやる気が湧いてきますよね。
すららは、クイズやアニメーションなどのゲーム感覚の要素を取り入れていて、子どもが「ちょっとやってみようかな」と思えるような設計になっています。
「勉強っぽくないのに、ちゃんと勉強できる」そんな感覚が、続ける力につながっていくんです。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
授業はすべてキャラクターのナビゲーション付きで、子どもが親しみを感じやすい構成になっています。
クイズやミニゲームのような問題もあり、正解するたびにキャラが褒めてくれるから、「もう1問だけやってみようかな」という気持ちに自然とつながります。
「楽しく勉強できる」って、やっぱり強いですよね。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD傾向のある子は、「すぐにフィードバックが返ってくる」ことにモチベーションを感じやすいと言われています。
すららでは、正解した瞬間に褒めてもらえたり、進捗が目に見えて確認できたりと、達成感を感じる工夫がたくさんあるんです。
「今やったことがすぐに評価される」という感覚が、継続のきっかけになってくれます。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
発達障害や不登校の子を支えるとき、どうしても親の負担が大きくなりがちですよね。
でもすららには「すららコーチ」という存在がいて、学習面のサポートを一緒に担ってくれるから、親子だけで頑張らなくて大丈夫なんです。
わからないところをすぐに相談できる人がいる安心感は、子どもにとっても保護者にとっても心強いですよ。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららコーチの多くは、発達障害や学習特性に関する知識を持っていて、子どものタイプに応じたアドバイスをしてくれます。
「集中力が続かない」「決まった時間にできない」といった悩みにも、否定せず寄り添ってくれるので、子ども自身が安心して取り組めるんです。
無理に矯正するのではなく、「その子らしさ」を活かして支えてくれるのがありがたいですね。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
学習計画って、親が全部組み立てようとするととても大変ですよね。
すららコーチは、学習の進捗や特性を見ながら、無理のないスケジュールを作ってくれます。
また、子どもがどこでつまずいているかをデータから分析して、保護者にも伝えてくれるので、「何をすればいいか」がとてもわかりやすくなります。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららは、教材のすべてがオンラインで完結する設計なので、どこかに通う必要はありません。
タブレットやPCが1台あれば、家でいつでも学習ができるから、環境づくりがとてもシンプルなんです。
通塾が難しい子や、外出に抵抗のある子でも、安心して学びを継続することができます。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららは、タブレットやPC1台で全教科が学べる設計なので、教材を買い足したり、プリントを管理したりといった手間がかかりません。
どこにいても、すぐに学習がスタートできる環境が整っていることで、保護者の管理の負担もグッと減ります。
道具の準備に手間取らず、すぐ取り組めるのも嬉しいポイントです。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校の期間が長くなると、「勉強の穴ができてしまうのでは?」と心配になりますよね。
でも、すららなら自宅でも着実に学習が進められるので、学校に通っていなくても学びを止めずにいられます。
「自分にもできた」という実感が自信につながり、再び社会とのつながりを持つきっかけにもなります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららを始めるときはワクワクしていたけれど、「子どもが続かなかった」「合わなかった」という理由でやめたいと考える方もいると思います。
そんなときに気になるのが、「解約ってどうするの?」「退会の違いって何?」という手続きの部分ですよね。
手続きを間違えてしまうと、「支払いが止まってなかった」「データが消えてしまった」といったトラブルになることもあるので、しっかり確認しておきたいところです。
この記事では、すららの【解約】と【退会】の違いをわかりやすく説明しながら、具体的な連絡方法まで丁寧に紹介していきます。
難しい手続きではないので、これを読めばスムーズに進められるはずです。
「いつまでに」「どこに」「何を伝えるのか」さえ押さえておけば、心配はありません。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめる時に混乱しがちなのが、「退会」と「解約」の違いです。
この2つは似ているようで、意味も手続き内容もまったく違うんです。
解約は「利用を一時ストップする」こと。
一方で退会は「すららの会員そのものをやめて、データもすべて消去する」ことになります。
「今後また使うかもしれない」と思っている方は、退会ではなく解約にしておくと安心です。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
解約は「一度すららをやめるけれど、また使うかもしれない」という方に向いています。
この手続きをすれば月額料金の支払いがストップし、教材の利用も止まりますが、データ自体はしばらく保管されます。
そのため、後から「また再開したい」と思ったときに、途中から学習を再開できるのがメリットです。
子どもに一時的なやる気の波がある場合も、解約という形を取っておくと便利です。
すららの退会は「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
退会は、完全にすららの利用を終了し、登録情報や学習履歴などのデータもすべて削除する手続きになります。
そのため、後から「またやってみよう」と思っても、以前のデータを引き継ぐことはできません。
「もう使う予定がない」「他の教材に切り替える」など、完全に区切りをつけたい場合は、退会を選ぶとスッキリします。
ただし、後戻りができないため、少し慎重に検討してから進めた方が安心です。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約手続きで基本になるのは、「すららコール」と呼ばれるサポートセンターへの電話連絡です。
マイページからのボタンひとつで解約できる仕組みにはなっておらず、少しアナログな方法ですが、そのぶん丁寧に対応してもらえるのが安心ポイントです。
電話では「いつで解約にしたいか」「本人確認のための情報」などを伝えるだけでOKなので、特に難しい操作はありません。
すらら側も慣れている対応なので、緊張せずに気軽に連絡して大丈夫ですよ。
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
最近のサービスはメールやマイページから手続きできることも多いですが、すららの場合は少し異なります。
解約の申し出は、メールやWEBフォームでは受け付けていません。
必ず「すららコール」と呼ばれるサポートセンターに電話する必要があります。
ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、本人確認をしっかり行うことで、間違いのない対応をしてもらえるというメリットもあります。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
解約の電話をかけた際には、登録している情報をもとに本人確認が行われます。
伝える内容としては、「契約者の氏名」「登録してある電話番号」「すららID」などです。
IDは、ログイン画面や登録完了メールなどで確認できますが、わからない場合でも丁寧に案内してもらえるので大丈夫です。
慌てず、わかる範囲で答えればOKですよ。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
すららの解約は、いつまで利用したいかを自分で指定できます。
電話の際に「今月いっぱいで解約したいです」といった希望日を伝えれば、それに沿って手続きが進みます。
ただし、日割り計算は行われないため、たとえば月の途中で解約しても、その月の利用料金はまるまる1か月分かかります。
タイミングを見て手続きするのがおすすめです。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを「完全にやめたい」と考えている場合は、解約だけでなく退会手続きも必要になります。
解約が完了した後に、別途「退会したい」と伝えることで、学習履歴や登録情報をすべて削除してもらうことができます。
こちらも電話で伝えるだけなので、難しい操作はありません。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
「解約のついでに退会もしたい」という場合は、電話のときにその旨を伝えるだけで大丈夫です。
「解約と退会、両方お願いします」と伝えると、オペレーターが手順をスムーズに案内してくれます。
その場で両方まとめて手続きできるので、二度手間にはなりません。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
退会をしないまま「解約のみ」にしておいても、料金はきちんと止まるので安心してください。
むしろ、「また再開するかもしれない」「子どもが再チャレンジしたくなるかも」と感じている場合は、退会しない方がスムーズに復帰できます。
完全にやめるつもりがなければ、解約だけでも何の問題もありません。
いは停止します)
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららって、使い方しだいで効果が変わるってご存じですか?
どんなに良い教材でも、「続かなかった」「効果がなかった」と感じてしまうのは、子どもに合った使い方ができていなかったケースが多いんです。
特に小学生は、学習の習慣がまだついていない時期。
集中力やモチベーションの波もあるので、「無理なく、でもしっかり続ける工夫」が必要なんです。
今回は、小学生におすすめのすららの使い方を、保護者目線でわかりやすく紹介します。
子どもが楽しみながら学びに向かえるコツを、1つずつ解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
「やらせなきゃ」ではなく、「一緒に楽しむ」姿勢で向き合うことが、結果的に一番の近道だったりするんです。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生がすららを効果的に使うには、「がんばりすぎない」「楽しみながら」「ちょっとずつ」が大事なポイントです。
最初から「毎日1時間やろう!」と意気込むよりも、「1日15分でもいいから、続けること」を目標にすると、ストレスも少なく継続しやすくなります。
親がそっと寄り添いながら、学びの習慣づくりをサポートするスタイルが、すららにはぴったりです。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
小学生の集中力は、長くても30分が限界という子がほとんどです。
だからこそ、「1回20〜30分×毎日少しずつ」がとても効果的なやり方です。
たとえば、夕食前に1単元だけ…というふうに決めておくと、自然とリズムができます。
「たくさんやる」よりも、「短くても毎日やる」方が記憶の定着にもつながります。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
小学生は「ごほうび」があるとやる気が続きやすいものです。
すららの学習を1ユニット終えるたびにシールを貼ったり、小さなお菓子をごほうびにしたりするだけでも、「また明日もがんばろう!」という気持ちにつながります。
ポイントは、「がんばったこと」をその場でしっかり認めてあげること。
その積み重ねが、学習習慣の土台になっていきます。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
特に低学年のお子さんは、「一緒にやろう!」と声をかけるだけで、驚くほど素直に取り組んでくれることがあります。
最初から子どもひとりに任せるのではなく、「ママも一緒に勉強しちゃおうかな」という軽いノリで関わってみてください。
横に座って声かけするだけでも安心感が生まれて、学習が楽しい時間に変わりますよ。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
子どもはつい、好きな科目ばかりに偏りがちですが、すららならAI診断で「どこが苦手なのか」がすぐにわかります。
最初にその診断を使って、苦手科目を中心に組み立てると、「できなかったことができるようになる」という実感を得やすくなります。
苦手から逃げずに向き合うことで、勉強に対する自信がどんどん育っていきます。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、部活や習い事、テスト、受験といった「やること」が一気に増えてきますよね。
そんな中で勉強をうまく進めるには、「目的に合わせて使い方を工夫する」ことがとても大切です。
すららは、ただ問題を解くだけではなく、予習・復習・テスト対策・学習計画までサポートしてくれる教材なので、使い方しだいで効果が大きく変わってきます。
ここでは、中学生がすららを効果的に使うためのポイントを4つご紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
すららは単元ごとに「まとめテスト」が用意されているので、学校の定期テストとの相性がとてもいいです。
学校から配られるテスト範囲表を見ながら、「今どの単元を復習するべきか」を逆算して計画を立てるのがおすすめです。
ただ毎日進めるだけでなく、テストに直結するように使うことで、点数アップにつながりやすくなります。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
部活が終わって夕方以降の時間は、どうしても疲れてしまいがちですが、「寝る前に15分だけすららをやる」と決めておくと、学習習慣が安定します。
長時間やるのではなく、「短時間で集中」するスタイルがすららには合っています。
毎日同じ時間に学ぶ習慣がつくと、自然と勉強に対するハードルが下がっていきます。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
中学生になると、自分で計画を立てるのが難しく感じる子も多くなります。
そんなときに心強いのが「すららコーチ」です。
学習の進め方や「どこでつまずいているのか」などを一緒に整理してくれるので、ただ進めるだけでなく「戦略的に学習する」感覚が身につきます。
わからないところはそのままにせず、コーチと一緒に解決していけるのが安心です。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
すららは「無学年式」だから、復習にも予習にも使えるのが大きな強みです。
特に英語や数学は、学校の授業に先回りしておくと、「あ、これ知ってる!」という安心感から授業がより理解しやすくなります。
授業の内容がスムーズに頭に入るようになると、自然と勉強が楽しくなっていきます。
復習は理解の定着に、予習は自信づくりに、と使い分けて活用するのがおすすめです。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、学習内容も一気にレベルアップし、授業についていけなかったり、進度に戸惑ったりすることも出てきますよね。
すららは中学生までの教材という印象もありますが、実は「基礎の取りこぼしを埋める」点で、高校生にもかなり有効なんです。
特に、模試や共通テストで思ったように得点できない子や、学校の授業と合わないと感じている子にとって、すららは“自分のペース”で学べる強い味方になります。
ここでは、そんな高校生向けのすらら活用法を紹介していきます。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生になると、「苦手なまま放置した単元」が積み重なっていることも多いですよね。
すららは無学年式なので、中学範囲までさかのぼって復習することができるのが強みです。
同時に、得意な単元は応用問題や発展内容に進めるので、「戻る」と「進む」をバランスよく使えるのがとても便利です。
今の学年にとらわれず、自分の理解度に合わせて進めていけるのが高校生にはちょうどいい使い方です。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
「授業の進度が早すぎる」「説明がわかりづらい」と感じたとき、すららは自分の理解に合わせて学べる教材として頼りになります。
自宅で落ち着いた環境で学べるから、焦らず、納得するまでじっくり取り組めるのが大きな魅力です。
周りのペースに合わせなくていい分、「本当にわかった」という実感を持てるのがすららのいいところです。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
共通テストや模試の点数が伸びない…という悩みの多くは、「基礎が抜けていること」が原因になっているケースが多いです。
すららは、基礎事項を丁寧に解説し、わかったつもりを防ぐ工夫がされているので、土台を固めるにはとても効果的です。
応用問題や過去問演習の前に、「まず基礎を完璧にしたい」と思っている高校生にはぴったりの使い方です。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生になると、「どれだけ勉強したか」を自分で管理する必要がありますよね。
すららには、学習時間や達成率をグラフで可視化する機能がついているので、「今日はここまで頑張った」と目に見える成果を確認できます。
自分のペースで取り組みながらも、「継続してる実感」を得られるので、モチベーション維持にもつながります。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校になると、学習の遅れだけでなく、生活リズムの乱れや、自己肯定感の低下といった問題も重なりがちです。
そんなときに大切なのは、「無理なく、自分のペースで学べる環境」を整えてあげること。
すららは、学校のような集団空間ではなく、自宅でひとりでも取り組める学習スタイルなので、不登校のお子さんにとってはとても心地よい教材になりやすいです。
ここでは、不登校の子がすららを活用して学びを取り戻すための、具体的な使い方をご紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校の生活では、昼夜逆転や不規則な過ごし方になりやすく、気づかないうちに心と体のリズムが乱れてしまうこともあります。
すららを「朝ごはんのあとに30分だけ」と決めるだけで、日常に小さなリズムが生まれます。
「ミニ時間割」を作って、学習と休憩のバランスを整えることで、無理のない形で生活を立て直す手助けになります。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
すららは、先生やクラスメイトの視線を感じることなく、自分の空間で静かに学べる設計になっています。
「見られている」「評価される」というプレッシャーがないからこそ、心が疲れている時期でも安心して取り組むことができます。
「わからない」と言えなかった子も、すららなら落ち着いて学習を進められることが多いんです。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
すららは、正解したときや目標を達成したときに、キャラクターが声をかけてほめてくれる仕組みがあります。
この「小さな成功体験」を積み重ねることが、失いかけた自信を少しずつ取り戻すきっかけになるんです。
「できたね」「よくがんばったね」と言ってもらえる体験が、勉強への前向きな気持ちを引き出してくれます。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校のお子さんは、「誰にもわかってもらえない」と感じて、心を閉ざしてしまうことがあります。
すららでは、学習コーチがやさしく声をかけてくれるので、親とはまた違う立場からのサポートが受けられます。
「こんな風にやってみようか?」と第三者の目線でアドバイスしてもらえることで、子どもの気持ちが少しずつ和らいでいくこともあります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
どんなに良い教材でも、「本当に効果があるの?」という不安ってありますよね。
特に、すららのように月額料金が発生する教材は、始める前に「実際に使っている人の声」が気になるもの。
ここでは、すららを実際に利用したご家庭から寄せられた、リアルな良い口コミを紹介します。
発達特性のあるお子さんや、不登校経験のある子、部活で忙しい中学生など、それぞれ違った背景を持つ方の声ばかりです。
「うちの子に合うかも」と感じるヒントがきっと見つかるはずなので、ぜひ読んでみてくださいね。
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
塾では緊張してしまっていたうちの子ですが、すららは自宅でできるし、ゲームっぽい雰囲気が楽しいようで、最初から抵抗なく始められました。
アニメのキャラクターが話しかけながら教えてくれるので、先生に質問する緊張感がなくて安心するみたいです。
自分のタイミングで進められるのが、合っていたんだと思います。
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
長時間集中するのが苦手なタイプの子なのですが、すららのアニメーション授業は視覚的にわかりやすいようで、飽きずに続けられています。
絵や図を見ながら進めるスタイルが合っていたみたいで、「これならできる」と自信を持ち始めました。
内容も難しすぎず、テンポよく進むのが良いですね。
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
不登校が続いていて、勉強が手つかずになっていたのですが、すららは無学年式なので、焦らず自分の理解に合わせて学べるのがありがたかったです。
何より、対面で人と関わらずに取り組めるのが、本人にとって安心だったようです。
「自分のペースでやっていいんだ」と思えることが、最初の一歩になりました。
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
部活が毎日遅くまであるので、通塾が難しかったのですが、すららなら帰宅後に30分だけでも取り組めるのが助かっています。
テスト前は、苦手な単元をピンポイントで復習できるので、勉強の効率も良いと感じています。
スマホのゲームをやる代わりに、すららを少し…という感じで続けられています。
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
手を動かして文字を書くことが負担になる子なので、紙のドリルはあまり続かなかったのですが、すららはタブレット上で操作できるので拒否感がありません。
本人も「これならできる」と自分から取り組んでくれるようになってきました。
アニメの声や色使いも優しくて、ストレスなく学べるのが良かったです。
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
すららなら親が何もしなくても進んでくれるかな?と思っていましたが、低学年の子にはやはりまだ難しい部分もありました。
ログインや操作に慣れるまでは、そばで一緒に見守ったり声をかけたりする必要がありました。
教材自体はやさしい内容ですが、もう少し「小さい子向けの補助モード」があったら、もっと気軽に取り組めるのに…と感じました。
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
始めたばかりの頃は自分から取り組んでいたのですが、気分の波が大きい不登校の子にとっては、調子が悪くなるとすぐ止まってしまいました。
サポートから連絡は来るものの、「どう再開させるか」は結局こちらの工夫にかかってくるなと感じます。
一人で学べるのが良さでもあり、難しさでもあると思いました。
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
高校生向けに使っていますが、基礎から丁寧に進むスタイルなので、進学校でハイレベルな内容に慣れている子には、少しゆるく感じるかもしれません。
共通テストの基礎固めには良いと思いますが、応用問題や実戦形式の演習がもっとあると、より幅広く活用できる気がします。
向き不向きは分かれると感じました。
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
キャラクターが出てきたり、アニメーションがあったりするのは最初は楽しく感じていたようですが、数週間たつと「飽きた」と言い始めました。
テンポや構成が似ているので、好奇心旺盛なタイプの子にはもう少し変化があるといいなと思いました。
ストーリー要素や、選べるモードなどが増えると、もっと楽しめる気がします。
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
月額としては塾よりはリーズナブルですが、半年、1年と長く続けるとなると、それなりの費用にはなってきます。
特に、兄弟で別々に使いたい場合は1人分ずつの契約が必要になるので、まとめて使うには少し負担を感じました。
内容は良いので、もう少し柔軟なプランがあるとありがたいです。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
すららって本当に大丈夫なサービスなの?という不安を感じる方、意外と多いんです。
特に「子どもに使わせる教材」って、料金や中身だけじゃなくて、**誰が作っているか**ってとても大事なポイントですよね。
長く安心して使いたいなら、運営元の信頼性もしっかり見ておきたいところです。
実はすららは、ただのオンライン教材ではなく、文部科学省から表彰されたり、公的機関と連携していたりと、教育現場でも高く評価されている会社が開発・運営しているんです。
この記事では、すららを提供している企業「すららネット」の基本情報をはじめ、どんな理念で作られているのか、どんな実績があるのかを紹介していきます。
サービスの中身とあわせて、「誰がどういう思いで運営しているのか?」もチェックしておくと、より安心して選ぶことができますよ。
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照:会社概要(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら うざい」というキーワードで検索されることがありますが、実際には「サポートが手厚すぎる」と感じる方が一定数いるからのようです。
すららは、コーチやサポートがこまめに連絡をくれるのが特徴なのですが、放っておいてほしいタイプの子や親にとっては、やや頻度が高く感じられることもあるようです。
ただ、それも見方を変えれば「丁寧なサポート」とも取れるので、お子さんやご家庭に合ったスタイルを見極めるのが大切です。
関連ページ:「すらら うざい」
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららに特別な「発達障害コース」があるわけではありませんが、発達障害のあるお子さんに向けたサポート体制や学習設計が整っているのが特徴です。
料金プランは通常コースと同じで、3教科・4教科・5教科から選ぶ形になっています。
学年に関係なく、自分のペースで学べる「無学年式」なので、つまずいている単元から無理なく始められる点が、多くの保護者に支持されています。
関連ページ:「すらら 発達障害 料金」
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららは、文部科学省のガイドラインに基づいて「出席扱い」になるケースもあります。
すべての学校で認められるわけではありませんが、すららを導入している自治体や学校と連携して、在宅学習でも出席扱いになるような取り組みが広がっています。
事前に学校や教育委員会に相談しながら進めることで、スムーズに認定される場合もあります。
関連ページ:「すらら 不登校 出席扱い」
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、時期によってキャンペーンコードが発行されることがあります。
申込時に専用ページや入力欄にキャンペーンコードを入力することで、初月の料金割引や入学金無料といった特典が適用される仕組みです。
キャンペーンは期間限定のものが多いため、公式サイトや案内メールで最新情報をチェックしておくのがおすすめです。
関連ページ:「すらら キャンペーンコード」
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は、まず「解約手続き」を電話で行ったうえで、希望があれば「退会依頼」もあわせて伝える形になります。
解約は、毎月の利用料金を止める手続きで、退会は会員情報や学習履歴をすべて削除する処理です。
電話で両方まとめて伝えることもできますし、解約だけにしてデータを残しておくことも可能です。
関連ページ:「すらら 退会」
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
基本的に、すららで必要になるのは「入会金」と「毎月の受講料」のみです。
教材の購入や、専用タブレットのレンタルなどは不要なので、自宅にあるPCやタブレットが使えれば、他に費用はかかりません。
インターネット接続環境が必要になるため、その通信費などは別ですが、追加教材の購入やプリント代などがかからないのは、保護者にとって安心材料のひとつです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは「1契約につき1人の学習管理」が基本になっています。
そのため、兄弟でそれぞれ進度や学習履歴を記録したい場合は、1人ずつ契約する必要があります。
ただし、家庭内でタブレットを共有することは可能なので、デバイスを別々に用意する必要はありません。
兄弟で一緒に使いたいときは、個別のIDとコースを契約するのがおすすめです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースでも英語を選ぶことができます。
「英語+国語+算数」の3教科構成で契約することが可能です。
英語の内容は、リスニングやアルファベットの基礎からスタートできるので、初めて英語に触れるお子さんでも安心です。
ネイティブ音声や音読チェックもあるので、英検や中学英語の準備としても使いやすい構成になっています。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららでは、学習コーチが一人ひとりの進度や特性に合わせて、学習計画の作成や進め方のアドバイスをしてくれます。
「つまずきポイント」や「苦手傾向」などもデータから分析して、個別に声をかけてくれるのが特徴です。
保護者からの相談にも応じてくれるので、「どうサポートしてあげたらいいかわからない…」と感じたときも、心強い存在になります。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
今や家庭用タブレット教材はたくさんの種類があって、「結局どれを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。
「すらら」もそのひとつですが、他の有名教材――たとえば「チャレンジタッチ」や「スマイルゼミ」、「スタディサプリ」などとは、内容もサポート体制も少しずつ違ってきます。
中でもすららは、「無学年式」「コーチによる個別サポート」「発達障害や不登校への対応」に強みがあるのが特徴です。
一方で、「タブレット学習=子どもだけでどんどん進められる」というイメージを持っていると、ちょっと違和感を感じるかもしれません。
この記事では、すららと他の家庭用タブレット教材をわかりやすく比較して、「どんな子に向いているのか?」「なにが違うのか?」というポイントを整理してご紹介します。
教材選びは、“どれが一番良いか”ではなく、“どれがうちの子に合うか”が大切。
その判断材料になれるよう、リアルな視点でお届けしますね。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
結論から言うと、「すらら=うざい」と感じるかどうかは、そのご家庭のスタイルやお子さんの性格によるところが大きいです。
たしかに、サポートがこまめだったり、アニメーションのキャラが賑やかだったりすることで、「しつこい」「合わない」と感じる声も一部にはあります。
でもその一方で、「不登校の子でも安心して使えた」「発達障害のある子にも合っていた」「塾よりも柔軟に学べる」といった肯定的な口コミも非常に多く見られます。
料金に関しても、学年別・教科数に応じて幅がありますが、サポートや学習環境の充実度を考えると、決して高すぎる印象ではありません。
特に「無学年式」「AI診断」「学習コーチの存在」は、他のタブレット教材にはない魅力で、「やる気に波がある子」や「家庭でしっかり見てあげられない場合」には強い味方になってくれるはずです。
最終的には、「自分の子に合うかどうか」を見極めることが一番大切。
少しでも気になる方は、無料体験や資料請求をして、まずは相性を試してみるのがおすすめです。
関連ページ:「すらら うざい」
